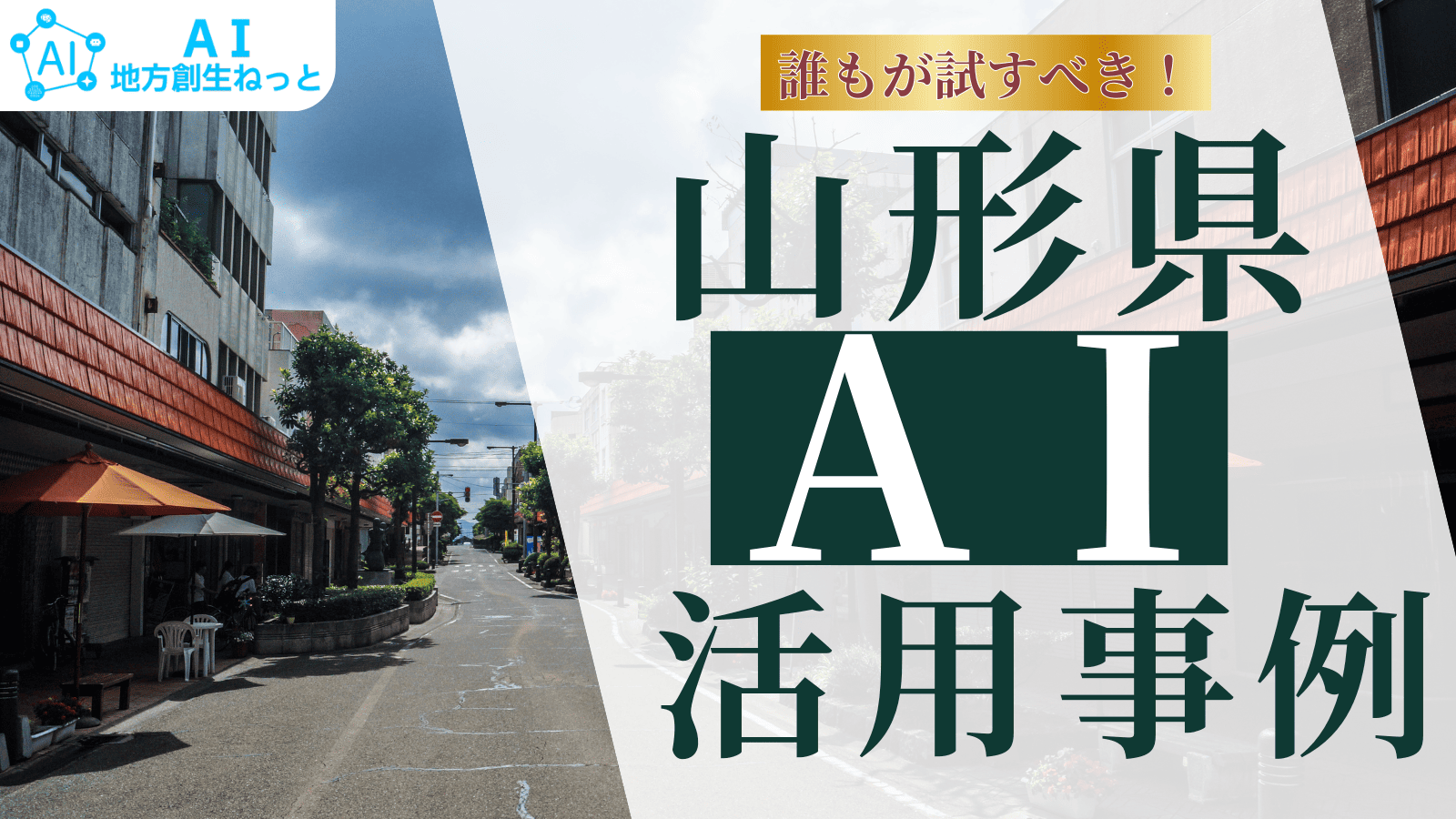昨今、山形県では少子高齢化をはじめとした地域の課題の解決に生成AIを用いる事例が増えてきています。
この記事ではそんな山形県の地方自治体や地場企業がどのように生成AIを活用しているか、AIを用いた地域活性化を行っているかを具体事例を元に紹介いたします!

水野倫太郎
(株)ICHIZEN HOLDINGS
代表取締役
慶應義塾大学経済学部卒。2017年米国留学時ブロックチェーンと出会う。2018年仮想通貨メディアCoinOtaku入社。2019年同社のCMO就任、2020年に東証二部上場企業とM&A。2022年(株)ICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ、Web3事業のコンサルティングをNTTをはじめとした大企業から海外プロジェクト、地方自治体へ行う。ブロックチェーンだけでなく生成AI導入による業務効率化を自治体中心に支援中。

監修 水野倫太郎
(株)ICHIZEN HOLDINGS
代表取締役
慶應義塾大学経済学部卒。2017年米国留学時ブロックチェーンと出会う。2018年仮想通貨メディアCoinOtaku入社。2019年同社のCMO就任、2020年に東証二部上場企業とM&A。2022年(株)ICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ、Web3事業のコンサルティングをNTTをはじめとした大企業から海外プロジェクト、地方自治体へ行う。ブロックチェーンだけでなく生成AI導入による業務効率化を自治体中心に支援中。
山形県のAI活用事例① 山形県庁:ChatGPT導入・試験運用
山形県庁は2023年、議事録や広報文など繰り返し発生する事務作業を効率化し、職員が企画や政策立案に集中できる体制を整えるため、生成AIの試験導入を決定しました。目的は“業務時間の圧縮”と“働き方改革”を同時に進めることです。
まず13種類の業務を対象にChatGPTを利用し、議事録要約・報告書ドラフト・広報文のたたき台などをAIが作成。職員は内容を確認・修正して仕上げるフローに変更しました。運用ルールとして「個人情報を入力しない」「AI出力は必ず人が確認する」など5原則を設定し、安全運用を徹底しています。
試行段階で文書作成時間がおおむね半分以下に短縮され、約65%の職員が効果を実感しました。2024年度からは対象業務をさらに広げる計画で、行政サービスの質向上と職員の創造的業務へのシフトが期待されています。
山形県のAI活用事例② 酒田市:全職員が使う“AI常備”庁舎の実現
酒田市は2023年、全職員に生成AIを開放し、庁内デジタル化を加速させるプロジェクトを開始しました。狙いは文書作成や調査業務を高速化し、市民対応のレスポンスを上げることです。
ChatGPTとBardを市職員のPCに常設し、挨拶文・議会答弁案・施策アイデアの下書きをAIが自動生成。職員は修正と最終決裁に注力します。セキュリティ基準を満たすガイドラインを定め、個人情報の入力禁止などを徹底しました。
導入直後から「半日かかる作業が約1時間で終了した」との報告が相次ぎ、文書作成工数が激減。浮いた時間は住民サービス向上に振り向けられ、市全体の業務スピードが底上げされました。今後は企画立案やデータ分析分野にもAI活用を拡大する予定です。
山形県のAI活用事例③ 山形市:24時間寄り添うAI×相談員
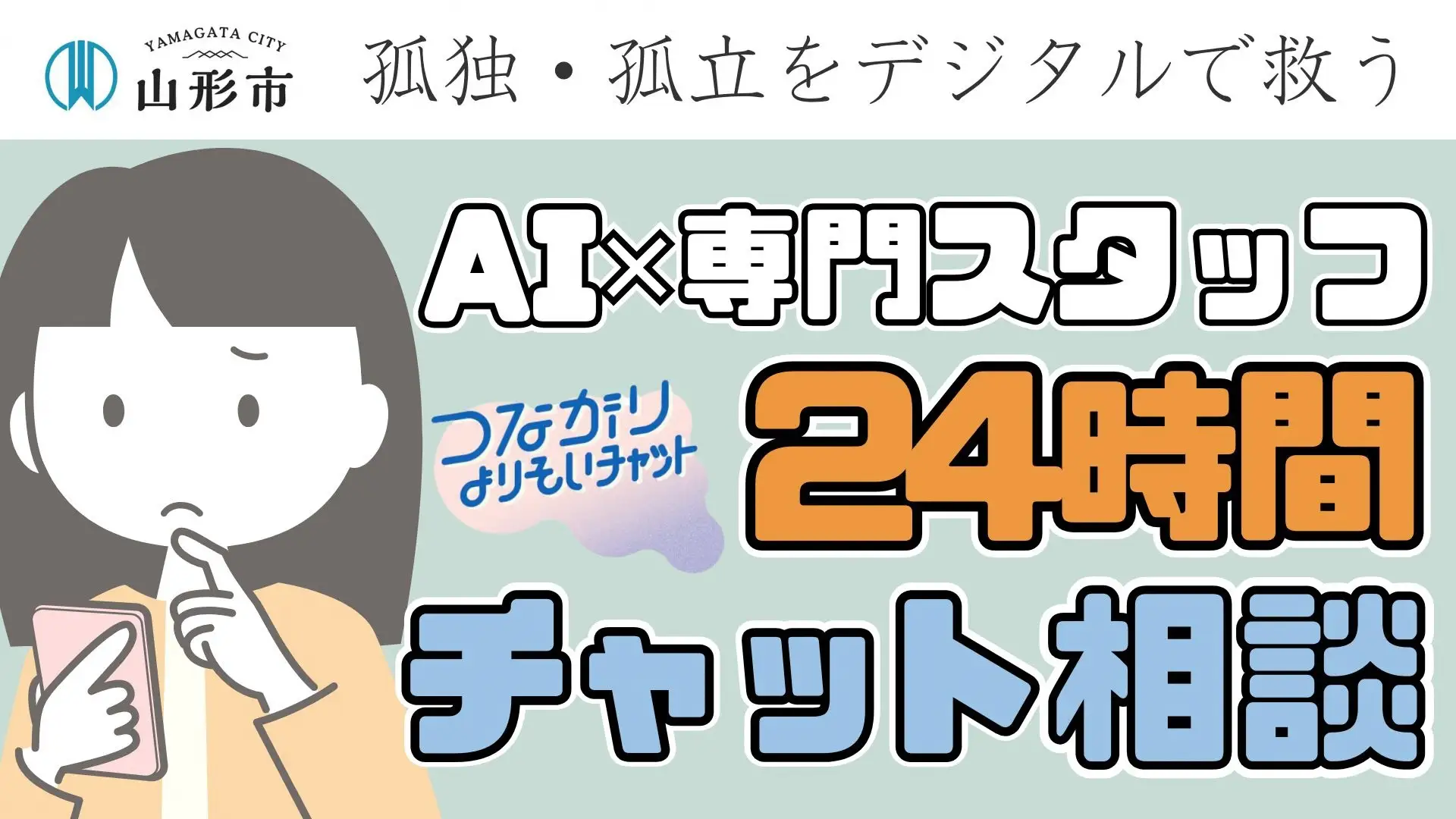
山形市は孤独・孤立対策として、2024年に24時間対応の傾聴型AIチャットボットを導入しました。目的は「いつでも相談できる安心窓口」をつくり、市民の心の健康を守ることです。
AIチャットがLINE上で初期相談を受け付け、内容を整理して専門相談員へエスカレーションします。相談員はAIがまとめた情報を基に迅速にアドバイスし、夜間や休日も切れ目なく支援できる仕組みです。
導入直後から夜間相談が増え、従来対応が難しかった時間帯の支援が可能になりました。相談員の負荷も平準化し、質の高い支援体制を維持。今後はAI応答の精度向上と地域ネットワーク連携による支援強化が期待されます。
山形県のAI活用事例④ 上山市:GPT-4で文書作成を半自動化
上山市は2024年、行政文書の作成・校正時間を短縮し、スピーディーな市民対応を実現するため、LGWAN対応のGPT-4ツールを導入しました。
政策提案書や報告書のドラフトをGPT-4が生成し、担当職員が内容を確認・加筆する二段構えのワークフローを新設しました。生成AI利用ガイドを全職員に共有し、適切なプロンプト例やチェック方法を教育しています。
導入後、文書作成所要時間が従来比で3〜5割短縮。浮いた時間を窓口改善や施策ブラッシュアップに充当できるようになりました。今後は議会資料や広報物への応用も視野に入れ、庁内のAI活用領域を拡大する計画です。
山形県のAI活用事例⑤ 川西町:exaBaseで“書類ラッシュ”を乗り切る
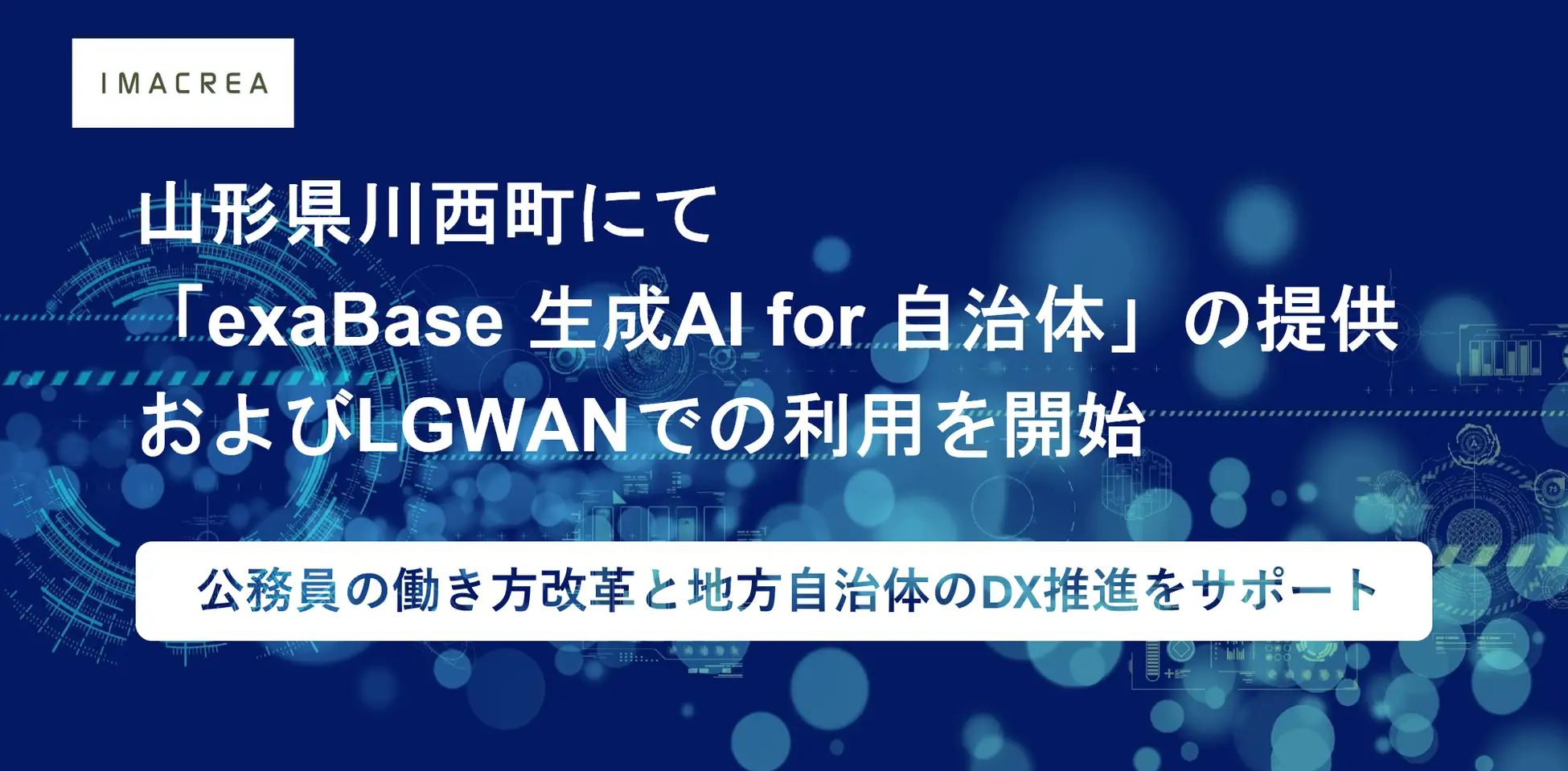
川西町は、繁忙期の書類ラッシュ対策として2024年に「exaBase 生成AI for 自治体」を導入しました。目的は広報文と議会答弁案づくりの負荷軽減です。
職員がプロンプトテンプレートを選択してAIに草案生成を依頼し、内容をチェック・修正して完成。LGWAN環境で動作し、入力情報が外部学習に使われない設計でセキュリティも担保しています。
広報文案づくりが従来の3分の1程度の時間で完了し、校閲漏れも減少。議会答弁作成では複数パターンを短時間に用意でき、議会準備の質とスピードが向上しました。今後は申請書類やマニュアル作成にも拡張予定です。
山形県のAI活用事例⑥ 山形大学:AIチャットボットで“いつでも問合せ可”のキャンパスへ
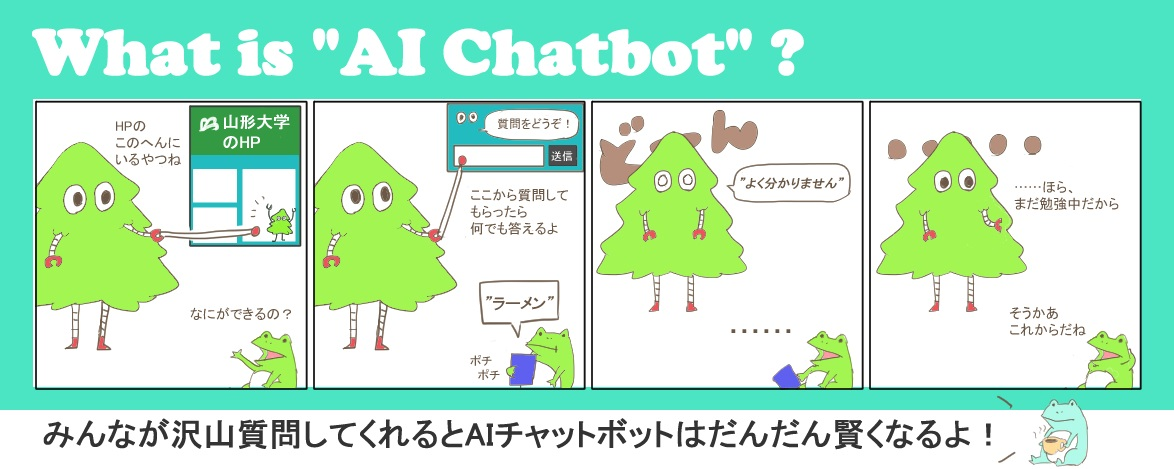
山形大学は2022年、学生サービス向上と事務負担軽減を目的に、深層学習型チャットボット「BEDORE Conversation」を全学導入しました。
学内 FAQ 約3,000 件を学習させたボットをLINE・Microsoft Teams に連携。履修手続きや奨学金、施設予約などの質問に 24 時間自動応答し、未解決の内容のみ職員が対応します。
夜間・休日の問合せ対応が可能になり、職員のメール・電話件数が大幅減。学生は即時に解決策を得られ、満足度が向上しました。将来的には生成AIを用いたガイダンス動画自動生成や多言語対応拡充が期待されます。
山形県のAI活用事例⑦ 山形県立米沢工業高校:授業と校務でAIリテラシーを体得
米沢工業高校は2024年、文科省の生成AIパイロット校に選定され、生徒のAI活用スキル育成と教員の校務効率化を図っています。
英語では ChatGPT を会話練習相手に、国語では短歌創作のアイデア出しに活用。教員は通知文や学級通信の草案を AI で作り、校務時間を短縮しています。
生徒は批判的思考を伴う“AIとの共創”を体験し、アウトプットの質が向上。教員は校務時間を平均 20%削減できたと報告されています。今後は画像生成AIを活用したデザイン教育への発展が期待されます。
山形県のAI活用事例 まとめ
山形県のにおける生成AIの活用事例を紹介してきました。
ちょっとした悩みを解決するために、生成AIの活用が山形県では積極的に行われています。
AIが当たり前になる自体を見据えて、高校・大学でも広くAIを利用する方向は他の地域でも参考になるかと思います。
生成AIの利活用、自治体内・社内導入で相談したい際には、ぜひ以下よりお気軽にお問い合わせください!