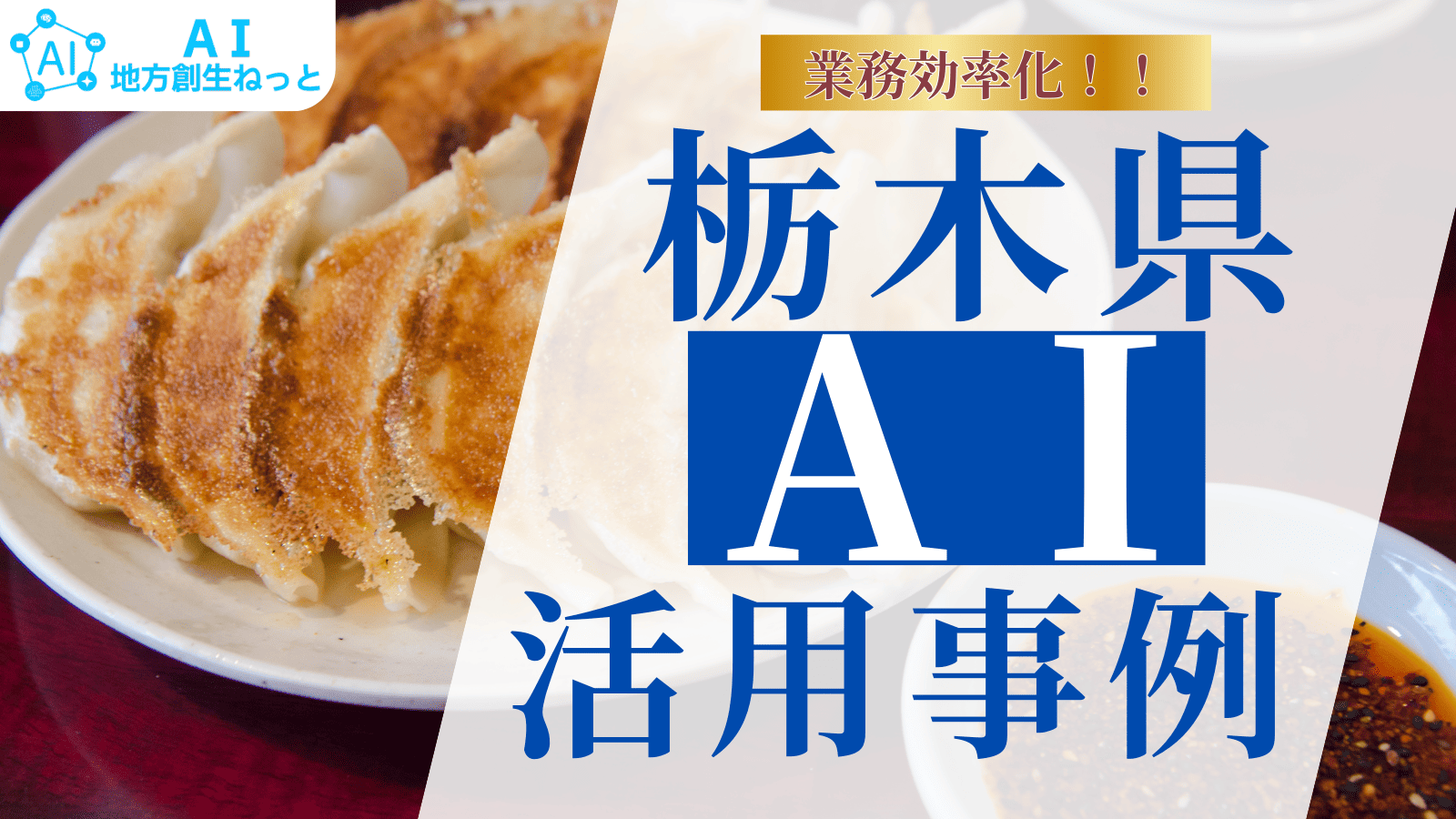近年、人工知能(AI)技術は目覚ましい発展を遂げ、私たちの社会や経済のあり方を大きく変えようとしています。特に、文章作成、画像生成、アイデア創出など、多岐にわたるタスクをこなす生成AIは、業務効率化や新たな価値創造の切り札として、さまざまな分野で活用が模索されています。地方創生においても、AIは地域課題の解決や魅力向上に貢献する強力なツールとなる可能性を秘めています。
本記事では、日本の関東地方に位置し、豊かな自然と独自の文化、そして活発な産業を有する栃木県に着目し、県内の地方自治体、学校法人、医療機関、インフラ企業、観光関連団体、そして民間企業が、生成AIをはじめとするAI技術をどのように活用し、業務効率化や地域活性化、いわゆる地方創生に取り組んでいるのか、具体的な事例を通じて詳しくご紹介します。
この記事は、自治体関係者の方々、地域活性化に情熱を注ぐビジネスパーソンの方々、そしてAI技術の社会実装に関心をお持ちのすべての方々にとって、栃木県における先進的な取り組みを知り、それぞれの地域や組織でのAI活用に向けたヒントや着想を得る一助となることを目指しています。各事例から、AI活用の具体的な方法論、導入によって得られた成果、そして今後の展望などを読み解き、未来の地域社会のあり方を共に考えていきましょう。

水野倫太郎
(株)ICHIZEN HOLDINGS
代表取締役
慶應義塾大学経済学部卒。2017年米国留学時ブロックチェーンと出会う。2018年仮想通貨メディアCoinOtaku入社。2019年同社のCMO就任、2020年に東証二部上場企業とM&A。2022年(株)ICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ、Web3事業のコンサルティングをNTTをはじめとした大企業から海外プロジェクト、地方自治体へ行う。ブロックチェーンだけでなく生成AI導入による業務効率化を自治体中心に支援中。

監修 水野倫太郎
(株)ICHIZEN HOLDINGS
代表取締役
慶應義塾大学経済学部卒。2017年米国留学時ブロックチェーンと出会う。2018年仮想通貨メディアCoinOtaku入社。2019年同社のCMO就任、2020年に東証二部上場企業とM&A。2022年(株)ICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ、Web3事業のコンサルティングをNTTをはじめとした大企業から海外プロジェクト、地方自治体へ行う。ブロックチェーンだけでなく生成AI導入による業務効率化を自治体中心に支援中。
宇都宮市:生成AIによる業務効率化と市民サービス向上への挑戦
栃木県の県庁所在地である宇都宮市は、早くからデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進に積極的に取り組み、行政サービスの質の向上と業務効率化を目指しています。その一環として、生成AIの活用にも注目し、具体的な取り組みを進めています。
活用事例の概要
宇都宮市では、特にデジタル政策課が中心となり、職員が日常業務において生成AIを活用し、資料作成の効率化やアイデア創出の質の向上を図っています。具体的には、文章作成支援、ブレインストーミングの活性化、さらにはローコード開発や翻訳、アンケート分析といった多様な業務での利用が試みられています。
活用方法と具体的な取り組み
同市における生成AIの活用は、単に既存業務を置き換えるのではなく、職員の能力を拡張し、より創造的な業務に時間を割けるようにすることを重視しています。具体的な活用方法としては、以下のようなものが挙げられます。
- 情報収集と全体像の把握: インターネット検索や参考書籍での調査と並行して、生成AIとの対話を通じて検討事項の全体像を迅速に把握し、論点を整理します。
- 資料作成支援: 企画書や報告書などの資料作成において、表現に迷った際に生成AIに複数の表現案を提示させ、その中から最適なものを選択したり、たたき台として活用したりしています。これにより、文章作成にかかる時間を大幅に短縮しています。
- アイデア創出(ブレインストーミング): 新規事業の立案や課題解決策の検討において、生成AIを壁打ち相手として活用し、多様な視点からのアイデア出しを促進しています。一人で考えるよりも思考が深まり、新たな気づきや斬新な発想が生まれることが期待されています。
- ローコード開発・翻訳・アンケート分析: Excelの関数やVBA(Visual Basic for Applications)といったローコードツールの作成支援、外国語文書の翻訳、アンケート結果の集計・分析といった専門的な知識が必要な業務においても、生成AIのサポートを受けることで、作業の効率化と質の向上が図られています。
さらに宇都宮市では、これらの試験的な活用を踏まえ、より本格的かつ全庁的なAI活用を推進する計画です。令和6年度には、全職員が利用可能なLGWAN(総合行政ネットワーク)対応の生成AIサービス「LoGoAIアシスタント」の導入を予定しており、それに伴い、情報セキュリティや倫理面に配慮した利用ガイドラインも策定する方針です。また、職員のAIリテラシー向上を目的とした研修も計画されており、CDXO(最高デジタルトランスフォーメーション責任者)補佐官によるプロンプトエンジニアリング研修などを通じて、より効果的なAI活用スキルの習得を支援していくとしています。
成果と今後の展望
宇都宮市における生成AIの試験的な活用は、2023年の春頃から始まり、徐々にその効果が表れ始めています。資料作成時間の短縮はもちろんのこと、職員一人ひとりの思考が整理され、新たなアイデアや視点を発見しやすくなったという声が上がっています。これにより、検討の質そのものの向上にも繋がっていると評価されています。
今後は、「LoGoAIアシスタント」の全庁展開を通じて、より多くの職員が生成AIを業務に活用することで、行政サービス全体の質の向上と、さらなる業務効率化が期待されます。宇都宮市のこうした先進的な取り組みは、他の自治体にとっても、AIを活用した地域課題解決や行政DX推進のモデルケースとなる可能性を秘めています。
(開始時期:2023年春頃から試験的に利用開始)
(宇都宮市生成AIガイドライン)
足利市:Google Workspace導入と将来的な生成AI活用によるDX推進
栃木県南西部に位置し、歴史と文化の薫り高い足利市は、行政サービスの向上と業務の効率化を目指し、デジタルトランスフォーメーション(DX)を積極的に推進しています。その中核的な取り組みの一つとして、Google Workspaceを全庁的に導入し、情報共有の円滑化や業務プロセスの自動化を進めるとともに、将来的にはGoogle Workspaceに搭載されている生成AI機能の活用も見据えています。
活用事例の概要
足利市では、従来のLGWAN(総合行政ネットワーク)環境におけるクラウドサービス利用の制約や、それに伴うテレワーク、ウェブ会議の実施の難しさといった課題を抱えていました。これらの課題を解決し、より柔軟で効率的な働き方を実現するため、LGWAN環境からローカルブレイクアウト(特定の通信をLGWAN網外のインターネットへ直接接続する方式)によりGoogle Workspaceへ接続するシステムを構築しました。これにより、全職員がGoogle Workspaceの豊富な機能を活用できるようになり、業務効率の大幅な向上が期待されています。
活用方法と具体的な取り組み
足利市におけるGoogle Workspaceの活用は多岐にわたります。主な活用ツールと取り組みは以下の通りです。
- コミュニケーションと情報共有の円滑化: Gmail、Googleカレンダー、Googleドライブ、Googleドキュメント、Googleスプレッドシート、Google Meet、Google Chatといったツール群を全庁的に導入。これにより、職員間の情報共有がスムーズになり、ペーパーレス化も促進されています。特に、資料の共同編集機能は、従来手間のかかっていた集計作業やマージ作業を大幅に省力化しました。
- 業務プロセスの自動化: Google Apps Scriptを活用し、職員の異動に伴うアカウント設定などの定型業務を自動化。また、ノーコード開発ツールであるAppSheetも導入し、現場の職員が自ら業務改善アプリを開発できる環境を整備しています。
- 柔軟な働き方の実現: BYOD(Bring Your Own Device:私物端末の業務利用)でのGoogleカレンダーやGoogle Chat、Google Meetの利用を可能にし、場所を選ばない柔軟な働き方を支援しています。これにより、テレワークや出張先での業務遂行が容易になりました。
- セキュリティとコスト効率の両立: 情報系・インターネット系システムをクラウド化することで、運用コストの削減とセキュリティレベルの向上を両立させています。
足利市では、これらのツール導入にあたり、2023年1月にGoogleの担当者と最初の協議を開始し、その後約半年間にわたるPoC(概念実証)を経て、2024年3月から本格運用を開始しました。職員の新しいツールに対する抵抗感も少なく、スムーズな導入と活用が進んでいると報告されています。
成果と今後の展望
Google Workspaceの導入により、足利市ではLGWAN環境の制約を克服し、クラウドサービスを最大限に活用した効率的な業務遂行が可能となりました。情報共有の迅速化、ペーパーレス化の推進、定型業務の自動化など、具体的な成果が表れています。
今後の展望として、足利市はGoogle Workspaceに搭載されている生成AI機能「Gemini for Google Workspace」の活用を視野に入れています。これにより、文章作成支援、アイデア創出、データ分析など、さらに高度な業務効率化と行政サービスの質の向上が期待されます。また、Chromebookを業務の中核端末として活用することも検討しており、さらなるコストメリットとセキュリティ強化を目指しています。
庁内の働き方改革も継続的に推進し、フリーアドレス化の導入や、業務データの外部持ち出しに関するセキュアな環境整備を進めることで、より創造的で生産性の高い職場環境の実現を目指していく方針です。足利市のこうした取り組みは、他の自治体におけるDX推進の参考となる先進事例と言えるでしょう。
(開始時期:2024年3月より本格運用開始。検討開始は2023年1月頃)
日光市:日本情報通信との連携による生成AI「NICMA」導入と行政サービス変革
世界遺産「日光の社寺」を擁し、国内外から多くの観光客が訪れる栃木県日光市は、行政事務の効率化と市民サービスの向上を目指し、ICT活用を積極的に推進しています。その一環として、日本情報通信株式会社(NI+C)との連携のもと、同社が提供する生成AIサービス「NICMA(ニクマ)」を導入し、庁内業務におけるAI活用を本格化させています。
活用事例の概要
日光市では、NI+Cからのデジタル人材派遣によるDX支援を受けながら、2024年4月より生成AI「NICMA」のトライアル利用を開始しました。同時に、職員向けの活用研修会を実施し、AIに対する理解と活用スキルの向上を図りました。トライアル期間中の効果検証と職員アンケートの結果を踏まえ、同年10月からは全部署での本格利用へと移行しています。この本格利用に先立ち、市は情報セキュリティや倫理的側面に配慮した運用ルールや注意事項をまとめた「生成AIガイドライン」を策定し、安全かつ効果的なAI活用に向けた体制を整備しました。
活用方法と具体的な取り組み
日光市における生成AI「NICMA」の活用は、主に庁内業務の効率化を目的としています。具体的な取り組みとしては、以下の点が挙げられます。
- デジタル人材の活用とDX推進: NI+Cから派遣されたデジタル専門人材が、日光市のDX推進をサポート。AI導入だけでなく、庁内全体のデジタル化戦略の策定や実行を支援しています。
- 生成AI「NICMA」のトライアルと本格導入: まずはトライアル利用を通じて、実際の業務におけるAIの有効性や課題を検証。職員からのフィードバックを収集し、本格導入に向けた準備を進めました。
- 職員向け研修会の実施: 生成AIの基本的な知識から、具体的な操作方法、効果的なプロンプトの作成方法など、実践的なスキルを習得するための研修会を実施。これにより、職員のAIに対する理解を深め、活用へのハードルを下げました。
- ガイドラインの策定: 個人情報や機密情報の取り扱い、著作権への配慮、生成される情報の正確性の確認など、AI利用における注意点を明確化したガイドラインを策定。これにより、職員が安心してAIを利用できる環境を整えました。
- 継続的な活用推進: 本格導入後も、職員向けのワークショップなどを継続的に開催し、さらなる活用事例の創出やノウハウの共有を促進していく計画です。NI+Cも引き続き伴走支援を行い、日光市のAI活用をサポートします。
成果と今後の展望
2024年4月に実施された研修会参加職員61名へのアンケートでは、9割以上が「自治体業務に生成AIが必要」と回答するなど、職員のAI活用に対する期待の高さが伺えます。また、研修後には、自ら生成AIを使いこなせる自信を持った職員が大幅に増加したという結果も出ています。
アンケートでは、具体的な活用イメージとして、「自動的な文章生成による時間短縮・手間の削減」「新たな発見や洞察の獲得」「イベントや事業の企画案作成への活用」といった前向きな意見や、「文書の要約・校正、情報活用、技術計算への応用」など、早期の本格導入を求める声が多数寄せられました。
日光市では、これらの成果と職員からの期待を踏まえ、今後も業務への生成AIの適用範囲を拡大していく方針です。また、AI活用の成果や利用上の課題を継続的に検討し、さらなる行政サービスの質の向上と業務効率化を目指していくとしています。日本情報通信との連携によるこの取り組みは、地方自治体におけるAI導入の先進的な事例として注目されます。
(開始時期:NICMAトライアル開始・研修会開催 2024年4月、全部署でのNICMA本格利用開始 2024年10月)
その他の市町におけるAI活用状況(総務省調査より)
これまでにご紹介した宇都宮市、足利市、日光市の先進的な取り組みに加え、栃木県内の他の市町においても、生成AIをはじめとするAI技術の活用に向けた動きが見られます。総務省が実施した令和5年度の調査によると、県内の一部の市や町で、業務へのAI導入や活用が検討・実施されていることが明らかになっています。
活用事例の概要
総務省の調査結果によれば、栃木県庁自体に加え、栃木市、鹿沼市、小山市、矢板市、下野市、茂木町、市貝町、野木町、塩谷町といった複数の自治体で、何らかの形でAIの業務活用が行われている、または具体的な検討が進められていることが示されています。ただし、各自治体における具体的なAIツールの種類、活用方法、導入時期、得られた成果といった詳細情報については、この調査からは必ずしも明らかになっていません。
活用方法と具体的な取り組み
調査結果では、AIの「活用方法」や「成果」について、「○(実施または効果あり)」「詳細あり」といった形で記載されている自治体がある一方で、「N/A(該当なしまたは情報なし)」となっているケースも見られます。これは、導入初期段階である、あるいは具体的な活用事例がまだ公表されていないといった理由が考えられます。
例えば、鹿沼市や矢板市では「活用方法:詳細あり」「成果:○」と報告されており、具体的な取り組みが進んでいる可能性が示唆されます。また、小山市では「開始時期:○」とされており、既に何らかの形でAI活用が始まっていることがうかがえます。茂木町や野木町、塩谷町でも、活用事例の概要や活用方法について言及があります。
これらの情報は断片的ではあるものの、栃木県内の多くの自治体が、行政サービスの質の向上や業務効率化を目指し、AI技術の可能性に注目し、その導入・活用に向けて動き出していることを示しています。
今後の展望
各市町におけるAI活用の取り組みは、まだ始まったばかりのところも多いと考えられます。今後、先進事例を参考にしながら、それぞれの地域の実情や課題に合わせた形でAI活用が進展していくことが期待されます。情報セキュリティの確保、職員のAIリテラシー向上、そして住民への丁寧な説明といった課題を乗り越えながら、AIが地方創生を力強く後押しするツールとして定着していくことが望まれます。
(出典:総務省 令和5年度地方公共団体における行政情報化の推進状況調査)
星の杜中学校・高等学校:AI評価ツール「Ai GROW」による非認知能力育成の最前線
栃木県宇都宮市に位置する学校法人宇都宮海星学園が運営する星の杜中学校・高等学校は、生徒一人ひとりの多面的な成長を支援するため、先進的な教育実践に取り組んでいます。その一環として、AIを活用した生徒評価ツール「Ai GROW(アイ・グロー)」を導入し、従来測定が難しかった非認知能力(思考力、表現力、判断力、主体性など)の客観的な可視化と育成に力を入れています。これは栃木県内の学校法人における特筆すべきAI活用事例の一つです。
活用事例の概要
星の杜中学校・高等学校では、生徒たちが変化の激しい現代社会を生き抜くために不可欠な、知識や技能だけではない「人間力」の育成を重視しています。この「人間力」の中核をなすのが非認知能力であり、これを客観的に把握し、効果的に伸ばしていくための手段として、株式会社EduLabが提供するAI評価ツール「Ai GROW」を有償で導入しました。このツールは、生徒の自己評価に加え、生徒同士の相互評価の結果をAIが分析・補正することで、25種類にも及ぶ多様な非認知能力を公正に可視化するものです。
活用方法と具体的な取り組み
「Ai GROW」の導入により、星の杜中学校・高等学校では以下のような具体的な取り組みを進めています。
- 非認知能力の定点観測: 定期的に「Ai GROW」による測定を実施し、生徒一人ひとりの非認知能力の伸びを時系列で把握します。これにより、個々の生徒の成長度合いに応じたきめ細やかな指導や声かけが可能になります。
- キャリア教育との連携: 測定結果は、生徒が自己の強みや課題を理解し、将来のキャリアを考える上での重要な参考資料となります。自己探究活動や進路指導と連携させることで、より主体的なキャリア形成を支援します。
- 総合型選抜への活用: 大学入試における総合型選抜などでは、学力だけでなく、主体性や協調性といった非認知能力も重視される傾向にあります。「Ai GROW」による客観的な評価データは、生徒が自己PRを行う際の有力なエビデンスとなり得ます。
- 面談資料としての活用: 個人面談や三者面談の際に、「Ai GROW」の測定結果を共有することで、生徒、保護者、教員が共通認識のもとで生徒の成長について話し合うことができます。具体的なデータに基づいたフィードバックは、生徒の自己肯定感を高め、さらなる成長を促します。
- 教育活動の効果検証と改善: 探究型学習やグループワーク、学校行事といった様々な教育活動が、生徒のどの非認知能力の育成に貢献したのかを客観的に検証できます。この分析結果を基に、教育プログラムの改善や新たな取り組みの企画に繋げています。
- 外部への情報発信: 保護者や学校関係者への活動報告、あるいは学校説明会などにおいて、「Ai GROW」を活用した教育実践の成果を具体的なデータとして示すことで、学校の教育方針や取り組みに対する理解と信頼を深めています。
成果と今後の展望
「Ai GROW」の導入は、星の杜中学校・高等学校において、生徒の非認知能力の伸長を具体的に可視化し、生徒自身の自己理解と客観的な自己評価を促すという大きな成果を生んでいます。また、教員にとっても、生徒の多面的な能力を把握し、より効果的な指導を行うための貴重なツールとなっています。
今後は、蓄積されたデータをさらに詳細に分析し、学級運営や学年運営、さらには学校行事全体の改善に活かしていく予定です。AIという先進技術を活用することで、生徒一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、未来を切り拓く力を育むという同学園の教育目標の実現が期待されます。
(開始時期:2023年8月10日プレスリリース発表。導入決定・準備期間はこれ以前と推察されます)
那須赤十字病院:オンプレミスLLMによる「退院サマリー」作成支援と医師の働き方改革
栃木県北部に位置し、地域医療の中核を担う那須赤十字病院は、医療従事者の業務負担軽減と医療の質の向上を目指し、先進的なICT技術の導入に積極的に取り組んでいます。その一環として、オンプレミス環境で稼働する大規模言語モデル(LLM)と生成AIアプリケーション開発基盤を活用し、医師の重要な業務の一つである「退院サマリー」作成の効率化に着手しました。これは、医療現場におけるAI活用の注目すべき事例です。
活用事例の概要
医師の業務の中でも、退院サマリーをはじめとする各種医療文書の作成は、多くの時間と労力を要する作業です。那須赤十字病院では、この負担を軽減し、医師がより多くの時間を患者の診療やコミュニケーションに充てられるようにするため、株式会社リコーが提供するソリューションを導入しました。具体的には、リコー製のGPUサーバー、同社が開発した700億パラメータを持つLLM、そして生成AIアプリケーション開発基盤「Dify」をオンプレミス環境に構築。これらを電子カルテシステムと連携させることで、退院サマリーのドラフトを自動生成するアプリケーションを開発・運用しています。
活用方法と具体的な取り組み
このシステムでは、医師が退院サマリーを作成する際に、まず電子カルテから必要な患者情報をAIが自動的に収集・要約し、サマリーのドラフトを生成します。医師は、このAIが作成したドラフトを基に、加筆・修正を行うことで、従来よりも大幅に短い時間で質の高い退院サマリーを完成させることができます。主な取り組みは以下の通りです。
- オンプレミス環境でのLLM運用: 患者情報という機密性の高いデータを取り扱うため、セキュリティを重視し、外部のクラウドサービスを利用せず、院内に設置したサーバーでLLMを運用しています。これにより、情報漏洩のリスクを最小限に抑えつつ、AIのメリットを享受できます。
- 電子カルテシステムとの連携: 既存の電子カルテシステムとAIシステムをスムーズに連携させることで、医師が特別な操作をすることなく、必要な情報をAIが自動的に取得できる仕組みを構築しています。
- 生成AIアプリ開発基盤「Dify」の活用: 「Dify」を用いることで、専門的なプログラミング知識がなくても、比較的容易にAIを活用した業務改善アプリケーションを開発・改修することが可能です。那須赤十字病院では、リコーによるDifyの活用教育も実施され、病院の事務職員が主体となって、さらなる業務改善を推進できる体制づくりも進められています。
- 段階的な導入と展開: まずは一部の医師による実業務での活用から開始し、効果や課題を検証しながら、順次院内全体へと展開していく計画です。
成果と今後の展望
この取り組みにより、那須赤十字病院では、退院サマリー作成にかかる時間の大幅な短縮と、それに伴う医師の事務的負担の軽減が期待されています。医師が文書作成業務から解放されることで、より患者一人ひとりに向き合う時間が増え、医療の質の向上にも繋がると考えられます。
リコーによる本ソリューションの発表は2025年4月30日であり、一部医師による実業務での活用が開始され、今後院内に展開予定とされています。将来的には、退院サマリーだけでなく、外来サマリーの作成など、他の医療文書作成業務へもAIの適用範囲を拡大していく計画です。那須赤十字病院のこの先進的な試みは、医師の働き方改革を推進し、持続可能な地域医療体制の構築に貢献するものとして、大きな注目を集めています。
(開始時期:リコーによる発表は2025年4月30日。一部医師による実業務での活用が開始されており、今後院内に展開予定。具体的なプロジェクト開始時期は記事に明記なし、ソリューション提供開始は2025年5月7日から)
帝京大学の学生プロジェクト:那須町における生成AIを活用した観光振興の試み
栃木県を代表する観光地の一つである那須町。その豊かな自然や温泉、レジャー施設は多くの観光客を惹きつけていますが、他の多くの観光地と同様に、情報発信の強化や新たな観光客層の開拓といった課題も抱えています。こうした中、帝京大学経済学部地域経済学科の五艘ゼミに所属する学生たちが、那須町の観光政策・観光事業における生成AI活用の可能性を探るという意欲的な研究プロジェクトに取り組みました。
活用事例の概要
このプロジェクトでは、学生たちが主体となり、2023年6月から2024年1月にかけて、那須町の観光の現状分析から、生成AI(主にChatGPT)を活用した具体的な観光客向けサービスのシミュレーションまでを一貫して行いました。具体的には、観光客からの問い合わせに対応するChatBotの制作や、特定のターゲット層に向けたモデル観光ルートとパンフレットの作成などを試みています。この取り組みは、観光分野における生成AI活用の実践的な可能性と課題を明らかにするものとして注目されます。
活用方法と具体的な取り組み
学生たちは、まず那須町の観光の現状を把握するため、観光事業者、行政担当者、そして実際に訪れる観光客へのインタビューやアンケート調査を実施し、それぞれの立場から見た課題を丁寧に整理しました。その上で、これらの課題解決に貢献しうる生成AIの具体的な活用シーンを、観光事業者、観光行政・関連団体、観光客という三つの視点から抽出しました。例えば、地域の魅力を伝える紹介文の自動作成、多言語対応の観光案内、パーソナライズされたモデルルートの提案などが挙げられます。
そして、これらのアイデアを具現化するためのシミュレーションとして、以下の二つの試みを行いました。
- ChatBot制作: ChatGPT-4.0と、ウェブサイト情報を基にFAQボットを容易に作成できる「DocsBot」というツールを連携させ、那須町観光協会の公式ウェブサイトの情報を学習させた問い合わせ対応ChatBotを制作しました。その際、生成AIが誤った情報を生成するリスクを考慮し、情報の正確性を担保するための工夫も凝らしています。
- モデルルート&パンフレット制作: ChatGPT-3.5を活用し、特に若者層をターゲットとした那須町のモデル観光ルートを考案。さらに、そのルートを紹介するためのパンフレットも作成しました。パンフレットには、ルートの魅力的な説明文、キャッチーなルートタイトル、そして目を引くキャッチコピーなどを盛り込みましたが、これらも生成AIの支援を受けて作成されました。ただし、パンフレットに使用するキャラクターの作成については、著作権の問題を考慮し、専門業者へ委託するという判断をしています。
成果と今後の展望
この研究プロジェクトを通じて、いくつかの重要な知見が得られました。
まず、ChatBot制作に関しては、月額数千円程度の低コストかつ1時間程度の短時間で、実用的な問い合わせ対応システムを構築できる可能性が示されました。これは、特に人手不足や予算に制約のある地方の観光協会や小規模事業者にとって、観光客からの問い合わせ対応を効率化する上で大きなメリットとなり得ます。
次に、モデルルートとパンフレットの制作においては、生成AIがアイデア出しや魅力的な文章作成に非常に有効である一方、地域資源に関する情報の正確性については注意が必要であることも明らかになりました。AIが生成した情報を鵜呑みにせず、必ず人間の目で確認し、必要に応じて修正を加えることの重要性が再認識されました。しかし、適切に活用すれば、ターゲット層に合わせた効果的な情報発信を効率的に行うことができると結論付けられています。
プロジェクト全体の考察として、学生たちは、生成AIが観光事業の実施や観光プランの立案における人材不足や資金不足といった課題を補う大きな可能性を秘めており、特にアイデア創出、文書作成、基本的な問い合わせ対応といった業務で有効活用できると結論付けました。ただし、AIが必ずしも地域の細かな魅力や文脈を完全に理解しているわけではないため、その点には十分な注意が必要であるという課題も提示しています。
この帝京大学の学生たちによる実践的な研究は、観光分野における生成AI活用の具体的な道筋と留意点を示唆するものであり、今後の地域観光の振興において大いに参考に値する事例と言えるでしょう。
(開始時期:プロジェクト期間は2023年6月~2024年1月。具体的な生成AIの利用開始時期はプロジェクト期間内と推察されます。資料の作成日は2023年11月8日)
デクセリアルズ株式会社:製造業における生成AIを活用した新規用途探索と事業成長
栃木県下野市に本社を構えるデクセリアルズ株式会社は、スマートフォンやノートパソコンなどのエレクトロニクス機器、そして電装化が進む自動車に不可欠な電子部品、接合材料、光学材料といった高機能材料の開発・製造・販売を手掛ける、日本を代表する素材メーカーです。同社は、変化の激しい市場環境の中で持続的な成長を遂げるため、そして社会課題の解決に貢献する次世代製品の開発を加速させるため、生成AI技術を新規用途探索に活用するという先進的な取り組みを開始しています。
活用事例の概要
デクセリアルズでは、自社が保有する高度な技術シーズ(種)を、新たな市場ニーズ(需要)に結びつけ、新規事業領域を開拓していくことが重要な経営課題となっています。しかし、この新規用途のアイデア創出プロセスは、従来、属人性が高く、膨大な情報の中から有望な組み合わせを見つけ出すのに多くの時間と労力を要するという課題を抱えていました。この課題を解決するため、同社はストックマーク株式会社が提供する生成AI技術とナレッジマネジメントサービスを活用し、新規用途探索の高精度化と高速化を目指す実証実験を2024年から開始。その結果、一定の優位性が見出されたことから、2025年3月には業務への本格導入を決定し、本格始動しています。
活用方法と具体的な取り組み
この取り組みでは、デクセリアルズが保有する特許情報や学術論文、社内調査レポートといった膨大な社内外の情報と、ストックマーク社が持つ「ナレッジグラフ構築技術」「データ構造化技術」「生成AI実装ノウハウ」を融合させています。具体的な活用方法は以下の通りです。
- 独自ナレッジグラフの構築: まず、デクセリアルズ社内の専門用語や技術的背景、さらには業界特有の言葉遣いまでをAIが深く理解するために、同社独自の「ナレッジグラフ」を構築します。これにより、単なるキーワード検索では見つけられないような、技術とニーズの間の潜在的な関連性をAIが発見できるようになります。このナレッジグラフは日々更新される情報にも対応し、常に最新の状況に基づいた探索を可能にします。
- 調査レポートの構造化と情報抽出: 同社が保有する独自の市場調査レポートや技術動向レポートは、図表や画像など複雑なレイアウトで構成されていることが多く、従来は情報の抽出や横断的な分析が困難でした。ストックマーク社の技術により、これらのレポートから正確に情報を抽出し、検索可能な形式に構造化することで、これまで見過ごされがちだった視覚情報を含むあらゆるデータを活用可能にし、事業機会や潜在ニーズの的確な把握を目指します。
- 技術(シーズ)起点と社会課題(ニーズ)起点の両面からのマッチング: 生成AIは、デクセリアルズが保有する特定の技術(シーズ)を起点として、その技術が応用可能な新たな用途を探索するだけでなく、逆に、市場のトレンドや社会が抱える課題(ニーズ)を起点として、それに応えることができる自社技術をマッチングさせる提案も行います。これにより、単に既存技術の用途を広げるだけでなく、真に市場から求められる技術開発や事業展開へと繋げることが期待されます。
成果と今後の展望
2024年から開始された実証実験では、特に「特許などの保有技術資料や社内調査レポートの構造解析」および「自社の技術情報を参照した生成AIによる新規用途の提示」といった点において、従来の手法と比較して明確な優位性が確認されました。これにより、新規用途アイデアの創出業務における属人性の排除、探索時間の大幅な短縮、そしてアイデアの質の向上が期待されています。
デクセリアルズでは、今後、この生成AIシステムと市場情報のマッチング精度、そして事業化の判断に資する情報提示の精度をさらに向上させることで、業務への本格的な定着を目指しています。この取り組みは、製造業におけるAIを活用した研究開発の効率化や、新たな事業機会の創出における先進事例として、大きな注目を集めています。素材メーカーという日本の基幹産業において、生成AIがイノベーションを加速させる可能性を示唆する重要な一歩と言えるでしょう。
(開始時期:実証実験開始 2024年、本格導入・業務適用開始時期 プレスリリース発表日(2025年3月3日)以降、順次)
終わりに:栃木県におけるAI活用の現状と未来への展望
本記事では、栃木県内における地方自治体、学校法人、医療機関、観光分野、そして民間企業による、生成AIをはじめとするAI技術の多様な活用事例をご紹介してきました。宇都宮市や足利市、日光市といった自治体での業務効率化の試みから、星の杜中学校・高等学校における非認知能力育成への応用、那須赤十字病院での医療文書作成支援、帝京大学の学生たちによる観光振興プロジェクト、さらにはデクセリアルズ株式会社のような製造業における新規用途探索に至るまで、それぞれの現場でAIが新たな価値を生み出し始めている様子がうかがえます。
これらの事例から見えてくるのは、AIが決して万能の解決策ではなく、それぞれの組織や地域が抱える具体的な課題に対し、目的意識を持って戦略的に導入・活用されてこそ、その真価を発揮するということです。また、職員や生徒、医療従事者といった現場の人々がAIを理解し、使いこなすための研修やガイドラインの整備、そして何よりも「AIと共に新しい価値を創造しよう」という前向きな姿勢が不可欠であることも共通しています。
栃木県におけるAI活用の取り組みは、まだ緒に就いたばかりの分野もあれば、既に具体的な成果を上げ始めている分野もあります。今後、これらの先進的な事例が県内全体へと波及し、さらには全国の他の地域における地方創生の取り組みにも示唆を与えることが期待されます。
もちろん、AIの活用には課題も伴います。情報セキュリティの確保、個人情報保護への配慮、AIが生み出す情報の正確性の検証、そしてAI技術の進化に伴う倫理的な問題など、乗り越えるべきハードルは少なくありません。しかし、これらの課題に真摯に向き合い、適切なルールメイキングと社会的なコンセンサス形成を進めていくことで、AIは地域社会の持続的な発展と、そこに住む人々の生活の質の向上に大きく貢献するでしょう。
本記事でご紹介した栃木県の多様なAI活用事例が、読者の皆様にとって、それぞれの地域や組織におけるAI活用の可能性を探る上での一助となり、ひいては日本全体の地方創生を加速させるための一つのきっかけとなれば幸いです。AIという強力なツールを手に、未来の地域社会を共にデザインしていく旅は、まだ始まったばかりです。