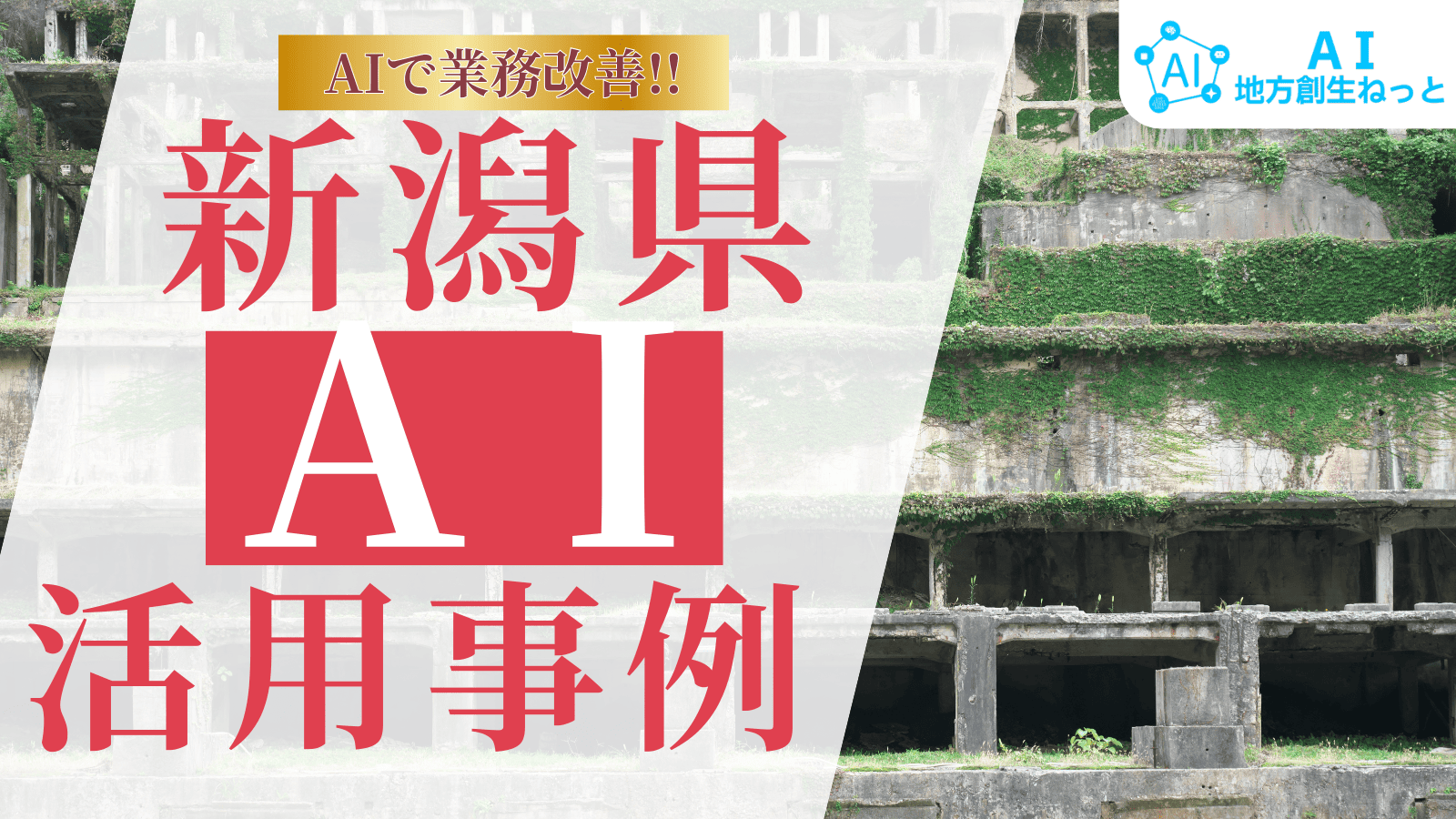新潟県では、生成AIをはじめとする人工知能技術を活用した地域課題の解決と地方創生に向けた取り組みが活発化しています。自治体による市民サービスの向上から、企業の業務効率化、さらには医療・教育分野での革新的な活用まで、多岐にわたる分野でAI技術が実装されています。
本記事では、新潟県内の自治体、学校法人、病院、民間企業における具体的なAI活用事例を詳しく紹介します。ChatGPTなどの生成AIから、IoT連携システム、予測分析まで、幅広いAI技術の実装状況と成果を通じて、地方におけるデジタル変革の現状と可能性を探ります。自治体関係者、地域活性化に関心のあるビジネス層、AI技術に興味をお持ちの方々にとって、実践的な参考情報となることを目指しています。

水野倫太郎
(株)ICHIZEN HOLDINGS
代表取締役
慶應義塾大学経済学部卒。2017年米国留学時ブロックチェーンと出会う。2018年仮想通貨メディアCoinOtaku入社。2019年同社のCMO就任、2020年に東証二部上場企業とM&A。2022年(株)ICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ、Web3事業のコンサルティングをNTTをはじめとした大企業から海外プロジェクト、地方自治体へ行う。ブロックチェーンだけでなく生成AI導入による業務効率化を自治体中心に支援中。

監修 水野倫太郎
(株)ICHIZEN HOLDINGS
代表取締役
慶應義塾大学経済学部卒。2017年米国留学時ブロックチェーンと出会う。2018年仮想通貨メディアCoinOtaku入社。2019年同社のCMO就任、2020年に東証二部上場企業とM&A。2022年(株)ICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ、Web3事業のコンサルティングをNTTをはじめとした大企業から海外プロジェクト、地方自治体へ行う。ブロックチェーンだけでなく生成AI導入による業務効率化を自治体中心に支援中。
新潟市|全職員対象の生成AI導入による業務効率化の先進事例
新潟市は2024年4月から、ChatGPTをはじめとする生成AI技術を全職員を対象に本格導入し、自治体業務の効率化において先進的な取り組みを展開しています。この取り組みは、地方自治体における生成AI活用のモデルケースとして注目を集めています。
活用概要と導入背景
新潟市の生成AI導入は、職員の業務効率化と市民サービスの質向上を目的として実施されています。特に文書作成業務、企画立案、情報整理といった知的労働の分野において、AIの支援により職員がより創造的で付加価値の高い業務に集中できる環境の構築を目指しています。
導入の背景には、人口減少に伴う職員数の制約がある中で、市民ニーズの多様化と行政サービスの高度化が求められているという課題があります。限られた人的リソースを最大限に活用し、効率的な行政運営を実現するため、生成AI技術の活用が不可欠と判断されました。
具体的な活用方法
新潟市では、生成AIを以下のような業務に活用しています。まず、各種行政文書の作成支援において、職員が作成する報告書、提案書、市民向け案内文書などの下書き作成や文章の改善提案にAIを活用しています。これにより、文書作成にかかる時間を大幅に短縮し、より質の高い文書の作成が可能になっています。
企画立案業務では、政策アイデアの発想支援、事業計画の構成検討、課題解決のためのアプローチ提案などにAIを活用しています。職員が抱える課題や目標をAIに入力することで、多角的な視点からの提案を得ることができ、より包括的で効果的な政策立案が可能になっています。
また、市民からの問い合わせ対応においても、FAQの作成支援や回答文案の作成にAIを活用し、迅速かつ適切な市民対応を実現しています。複雑な制度説明や手続き案内についても、AIの支援により分かりやすい説明文の作成が可能になっています。
成果と効果
新潟市の生成AI導入により、具体的な成果が現れています。文書作成業務においては、従来の作業時間を平均30-40%短縮することができ、職員がより戦略的な業務に時間を割けるようになりました。特に定型的な文書作成業務では、AIによる下書き作成により、職員は内容の精査と改善に集中できるため、文書の質も向上しています。
企画立案業務では、AIからの多様な提案により、職員の発想の幅が広がり、より革新的なアイデアの創出が促進されています。従来は限られた視点からのアプローチに留まりがちだった政策検討において、AIの支援により多角的な検討が可能になり、政策の実効性向上に寄与しています。
市民サービスの面では、問い合わせ対応の迅速化と質の向上が実現されています。AIによる回答文案の作成支援により、職員は短時間で適切な回答を提供できるようになり、市民満足度の向上につながっています。
今後の展望と課題
新潟市では、生成AI活用の更なる拡大を計画しています。現在の文書作成支援から、より高度な政策分析、データ分析支援、市民との対話支援などへの活用拡大を検討しています。また、他の自治体との連携により、生成AI活用のベストプラクティスの共有と標準化も進める予定です。
一方で、個人情報保護、情報セキュリティの確保、職員のAIリテラシー向上といった課題への対応も重要視されています。継続的な研修の実施と、適切な利用ガイドラインの整備により、安全で効果的なAI活用の推進を図っています。
糸魚川市|AI観光大使「AIさくらさん」による観光DXと人手不足解消
糸魚川市は2023年8月1日から、AI観光大使「AIさくらさん」を糸魚川駅改札前観光案内所に導入し、観光業界の人手不足解消と観光サービスの質向上を同時に実現する革新的な取り組みを展開しています。この事例は、地方都市における観光DXの成功モデルとして全国から注目を集めています。
活用概要と導入背景
「AIさくらさん」は、株式会社ティファナ・ドットコムが開発したAI接客システムで、ChatGPTや画像生成AIなどの最新AI技術を搭載しています。糸魚川市観光大使「ヒスイレディ」の衣装を着用し、観光客からの様々な質問に24時間365日対応できる体制を構築しています。
導入の背景には、観光案内所における深刻な人手不足があります。従来は限られた職員で観光案内業務を行っていましたが、観光客の増加と多様化するニーズに対応するためには、より効率的で持続可能なサービス提供体制が必要でした。また、コロナ禍を経て非接触型サービスへの需要も高まっており、AI技術の活用が最適解として選択されました。
具体的な活用方法
「AIさくらさん」は、観光案内所において多岐にわたる業務を担当しています。主な機能として、観光スポットの案内、イベント情報の提供、交通アクセスの説明、宿泊施設の紹介、地域グルメの案内などがあります。特に注目すべきは、単なる情報提供にとどまらず、観光客の興味や滞在時間に応じたカスタマイズされた観光プランの提案も行っている点です。
システムは音声認識と自然言語処理により、観光客の質問を正確に理解し、適切な回答を生成します。また、画像生成AI機能により、観光スポットの写真や地図を表示しながら説明することで、より分かりやすい案内を実現しています。多言語対応機能も搭載されており、外国人観光客にも対応可能です。
さらに、「AIさくらさん」は観光客との対話データを蓄積・分析し、よく寄せられる質問や観光客のニーズを把握する機能も持っています。この分析結果は、観光政策の立案や新たなサービス開発に活用されています。
成果と効果
「AIさくらさん」の導入により、糸魚川市は複数の具体的な成果を上げています。最も顕著な効果は人手不足の解消で、従来5名程度の人員が必要だった観光案内業務を、AIが24時間365日対応することで大幅に効率化しました。これにより、職員はより戦略的な観光振興業務に集中できるようになっています。
観光客の満足度向上も重要な成果です。24時間対応により、早朝や夜間に到着する観光客にも適切な案内を提供できるようになりました。また、子どもたちからは「さくらちゃん」として親しまれており、新たな観光の魅力として認知されています。
データ分析による政策立案支援も大きな効果の一つです。観光客からの質問分析により、「駅弁購入場所の質問が多い」という傾向が判明し、これを受けて糸魚川市では駅弁開発プロジェクトが発足しました。このように、AIが収集するデータが具体的な地域振興策につながっている点は特筆すべき成果です。
今後の展望と課題
糸魚川市では、「AIさくらさん」の機能拡張を計画しています。QRコード決済機能の導入により、観光商品の販売やイベントチケットの購入なども可能にする予定です。また、他の観光案内所への遠隔サポート機能の実装により、市内全体の観光案内体制の強化を図る計画もあります。
技術面では、より高度な対話能力の向上と、リアルタイムでの観光情報更新機能の強化が課題となっています。また、観光客のプライバシー保護と、収集データの適切な活用バランスの確保も重要な検討事項です。
この取り組みは、地方都市における観光DXの成功事例として、他の自治体からも注目を集めており、糸魚川市は知見の共有と横展開にも積極的に取り組んでいます。
佐渡市|富士通AI「Wide Learning」による子育て支援の革新的取り組み
佐渡市は2024年2月から、富士通株式会社と連携してこども家庭庁の「こどもデータ連携実証事業」に参画し、AI技術を活用した支援を必要とするこどもと家庭の早期発見システムを構築しています。この取り組みは、社会課題解決におけるAI活用の先進事例として、全国の自治体から注目を集めています。
活用概要と導入背景
佐渡市では、富士通が開発した説明可能なAI「Wide Learning」を活用し、教育・保育・福祉・医療などの分野を越えたデータ連携により、支援を必要とするこどもと家庭の早期発見を目指しています。この実証事業は2024年2月28日から3月31日まで実施され、その後も継続的な運用が予定されています。
導入の背景には、従来の支援体制における構造的な課題があります。これまでのこどもや家庭への支援は、当事者や関係者からの相談や通報が前提となっており、支援を必要とするこどもや家庭の発見が遅れ、事案が深刻化してから対応するケースが多く見られました。佐渡市は2020年3月に策定した「第2期佐渡市こども・子育て支援事業計画」のもと、地域や教育機関、医療・保健・福祉関連機関と緊密に連携した支援を行っていましたが、より予防的で効果的な支援体制の構築が急務となっていました。
具体的な活用方法
「Wide Learning」は、データに含まれる重要な性質の発見や、誤った予測の原因究明ができる説明可能なAIとして設計されています。佐渡市では、庁内の部局をまたがる教育・保育・福祉・医療などの分野のデータを、プライバシーを尊重しつつ法令を遵守した上で取得し、「こども統合データベース」として構築しました。
このシステムでは、AIが対象者ごとに支援が必要となる可能性を分析し、その結果を専門的な知見を持つ佐渡市の職員が参考にして支援要否を判断する仕組みになっています。重要なのは、AIが最終的な判断を行うのではなく、人間の専門職が判断を行う際の支援ツールとして機能している点です。
データ連携においては、個人情報保護法をはじめとする関連法令を厳格に遵守し、データの匿名化処理や適切なアクセス制御を実施しています。また、AIによる分析結果の透明性を確保するため、「Wide Learning」の説明可能性機能を活用し、なぜその判断に至ったかの根拠を明確に示すことができます。
成果と効果
実証事業を通じて、佐渡市では複数の重要な成果を確認しています。最も顕著な効果は、支援が必要なこどもや家庭の早期発見能力の向上です。従来は相談や通報を待つ受動的な対応が中心でしたが、AIによる予測分析により、潜在的なリスクを抱える家庭を事前に特定し、予防的な支援を提供できるようになりました。
職員の業務効率化も重要な成果の一つです。膨大な量のデータを人力で分析することは現実的ではありませんでしたが、AIによる自動分析により、職員はより重要な判断業務や直接的な支援活動に集中できるようになりました。また、AIの分析結果により、支援の優先順位付けがより客観的かつ効率的に行えるようになっています。
さらに、部局間のデータ連携が促進されたことで、これまで個別に管理されていた情報が統合的に活用されるようになり、より包括的な支援計画の策定が可能になりました。教育、保健、福祉の各分野の情報を総合的に分析することで、多角的な視点からの支援アプローチが実現されています。
今後の展望と課題
佐渡市と富士通は、今後各関係機関と連携し、支援が必要なこどもと家庭への具体的な支援までの仕組みづくりを進める予定です。最終的には、支援が必要なこどもや家庭に有益なサービスと情報を届けるアウトリーチ型の支援の実現を目指しています。
技術面では、AIの予測精度の更なる向上と、より多様なデータソースとの連携拡大が課題となっています。また、職員のAI活用スキルの向上と、適切な判断を行うための継続的な研修体制の整備も重要な取り組み事項です。
この実証事業は、こども家庭庁の政策にも影響を与える可能性があり、全国の自治体における子育て支援のデジタル化推進のモデルケースとして期待されています。佐渡市の取り組みは、地方自治体におけるAI活用による社会課題解決の先進事例として、今後も注目を集め続けるでしょう。
上越市|全職員対象のChatGPT導入とセキュリティ対策の両立
上越市は2024年4月1日から、文書生成AI「ChatGPT」の本運用を開始し、全職員を対象とした生成AI活用による業務効率化を推進しています。この取り組みは、セキュリティ対策と利便性の両立を図った先進的な事例として、他の自治体からも注目を集めています。
活用概要と導入背景
上越市のChatGPT導入は、職員の業務効率化を主目的として実施されています。特に文章や資料の構成検討、企画のアイディア検討などの知的労働において、AIの支援により職員がより創造的で付加価値の高い業務に集中できる環境の構築を目指しています。
導入の背景には、行政業務の複雑化と職員の業務負荷増大があります。市民ニーズの多様化に伴い、より質の高い行政サービスの提供が求められる一方で、限られた人的リソースの中で効率的な業務運営を実現する必要がありました。生成AI技術の活用により、定型的な業務の効率化を図り、職員がより戦略的で創造的な業務に時間を割けるようにすることが重要な課題となっていました。
具体的な活用方法
上越市では、職員が業務で使用する職員用ビジネスチャット「Logoチャット」の中で、ChatGPTに質問を入力し回答が得られる形式のシステムを構築しています。この統合型アプローチにより、職員は普段使用しているコミュニケーションツール内でシームレスにAI機能を活用できます。
主な活用場面として、各種行政文書の作成支援があります。報告書、提案書、市民向け案内文書などの下書き作成や文章の改善提案にChatGPTを活用し、文書作成にかかる時間を大幅に短縮しています。また、政策立案業務では、課題分析、解決策の検討、事業計画の構成検討などにAIを活用し、多角的な視点からの政策検討を可能にしています。
市民対応業務においても、問い合わせ内容に対する回答文案の作成や、複雑な制度説明の分かりやすい文章化にChatGPTを活用しています。これにより、迅速かつ適切な市民対応が実現されています。
セキュリティ対策と安全な利用環境
上越市のChatGPT導入において特筆すべきは、徹底したセキュリティ対策です。システムでは、入力された情報がAIの学習に使用されないよう設定されており、職員が入力した情報が外部に流出したり、他の用途に使用されたりするリスクを排除しています。
個人情報保護機能として、個人情報の疑いがある文章が入力された際に警告を発する機能が実装されています。これにより、職員が誤って個人情報を含む内容を入力することを防ぎ、情報漏洩リスクを最小限に抑えています。
また、利用状況を確認できる機能により、システムの適切な使用状況をモニタリングし、不適切な利用の早期発見と対応が可能になっています。これらの機能により、安全で効果的なAI活用環境が構築されています。
ガイドライン策定と職員教育
上越市では、生成AI利用にあたり、個人情報保護などの注意事項をまとめた「生成AIに関するガイドライン」を策定しています。このガイドラインは、職員が安全かつ効果的にAIを活用するための具体的な指針を提供しており、利用場面ごとの注意点や禁止事項が明確に定められています。
ガイドラインの内容は、国の動向や技術の進歩を踏まえて定期的に見直しが行われる予定であり、常に最新の状況に対応した適切な利用指針を維持する体制が整備されています。
職員教育においては、AI技術の基本的な理解から、具体的な活用方法、セキュリティ上の注意点まで、包括的な研修プログラムが実施されています。これにより、全職員が適切にAI技術を活用できる能力の向上を図っています。
成果と効果
上越市のChatGPT導入により、複数の具体的な成果が確認されています。業務効率化の面では、文書作成業務において従来の作業時間を平均30-40%短縮することができ、職員がより戦略的な業務に時間を割けるようになりました。
政策立案業務では、AIからの多様な提案により職員の発想の幅が広がり、より革新的で実効性の高い政策の検討が可能になっています。従来は限られた視点からのアプローチに留まりがちだった政策検討において、AIの支援により多角的な検討が実現されています。
市民サービスの質向上も重要な成果です。問い合わせ対応の迅速化と回答の質向上により、市民満足度の向上が確認されています。また、職員の業務負荷軽減により、より丁寧で親身な市民対応が可能になっています。
今後の展望と課題
上越市では、ChatGPT活用の更なる拡大を計画しています。現在の文書作成支援から、より高度な政策分析、データ分析支援、市民との対話支援などへの活用拡大を検討しています。また、他の自治体との連携により、生成AI活用のベストプラクティスの共有と標準化も進める予定です。
技術面では、より高度な対話能力の向上と、市の業務に特化したカスタマイズ機能の実装が課題となっています。また、職員のAIリテラシーの継続的な向上と、新たな技術動向への対応も重要な取り組み事項です。
上越市の取り組みは、自治体における生成AI活用のモデルケースとして、全国の自治体から注目を集めており、知見の共有と横展開にも積極的に取り組んでいます。
新潟大学・新潟大学医歯学総合病院|NTT東日本との医療文書作成支援AI共同研究
新潟大学と新潟大学医歯学総合病院は、NTT東日本と連携して2025年5月26日から2026年3月31日まで、大規模言語モデル「tsuzumi」を活用した医療文書作成支援AIモデルの実証事業を実施しています。この取り組みは、医師不足という深刻な社会課題の解決に向けた革新的なアプローチとして、医療業界から大きな注目を集めています。
活用概要と導入背景
この共同研究は、医師不足および医師の偏在という課題解決を目的として実施されています。NTTが開発した「tsuzumi」は、軽量でありながら世界トップレベルの日本語処理性能を持つ大規模言語モデル(LLM)として設計されており、医療分野特有の専門用語や複雑な文書構造に対応できる高度な言語処理能力を有しています。
導入の背景には、医療現場における深刻な人手不足と業務負荷の増大があります。特に地方の医療機関では、限られた医師数で多様な医療ニーズに対応する必要があり、診療以外の文書作成業務が医師の大きな負担となっています。診療録の作成、各種報告書の作成、患者・家族への説明文書の作成など、医師が行う文書作成業務は膨大な量に上り、これらの業務効率化が急務となっていました。
具体的な活用方法
「tsuzumi」を活用した医療文書作成支援AIモデルは、医療現場の様々な文書作成業務を支援します。主な機能として、診療録の下書き作成、検査結果の要約、患者向け説明文書の作成、各種医療報告書の構成提案などがあります。
システムは、医師が入力した症状や検査結果などの基本情報を基に、適切な医療文書の下書きを自動生成します。生成された文書は、医師が内容を確認・修正することで、最終的な文書として完成させる仕組みになっています。重要なのは、AIが最終的な医療判断を行うのではなく、医師の文書作成業務を支援するツールとして機能している点です。
また、医療分野特有の専門用語や略語、複雑な症例記述にも対応できるよう、「tsuzumi」は医療分野のデータで追加学習が行われています。これにより、一般的な言語モデルでは対応困難な医療文書の特殊性に適切に対応できます。
セキュリティと個人情報保護
医療分野でのAI活用において最も重要な課題の一つが、患者の個人情報保護とセキュリティの確保です。この実証事業では、医療情報の機密性を確保するため、厳格なセキュリティ対策が実装されています。
患者の個人情報は適切に匿名化処理が行われ、AIの学習データとして使用される際には個人を特定できない形に加工されています。また、システムへのアクセス制御、データの暗号化、監査ログの記録など、医療情報システムに求められる高度なセキュリティ要件を満たす設計となっています。
さらに、生成された文書の品質管理と医療安全の確保のため、AI生成文書は必ず医師による確認・承認を経る仕組みが確立されています。これにより、AI技術の利便性を活用しながら、医療の質と安全性を確保する体制が構築されています。
期待される成果と効果
この実証事業により、複数の重要な成果が期待されています。最も直接的な効果は、医師の文書作成業務にかかる時間の大幅な短縮です。従来、診療録の作成や各種報告書の作成に要していた時間を50-60%削減することを目標としており、これにより医師がより多くの時間を患者の診療に集中できるようになります。
医療サービスの質向上も重要な期待効果です。文書作成業務の効率化により、医師が患者とのコミュニケーションにより多くの時間を割けるようになり、より丁寧で質の高い医療サービスの提供が可能になります。また、標準化された文書フォーマットの活用により、医療情報の共有と連携も向上することが期待されています。
地域医療の持続可能性向上も重要な成果の一つです。医師の業務負荷軽減により、地方の医療機関での勤務継続意欲の向上や、新たな医師の確保にも寄与することが期待されています。
今後の展望と課題
実証事業の成果を踏まえ、新潟大学とNTT東日本は、より広範囲での医療AI活用の展開を計画しています。新潟県内の他の医療機関への展開や、より高度な医療AI機能の開発などが検討されています。
技術面では、より多様な医療文書への対応拡大と、医師の個別の文書作成スタイルに適応できるカスタマイズ機能の実装が課題となっています。また、他の医療情報システムとの連携強化により、より包括的な医療DXの実現を目指しています。
この取り組みは、地方における医療DXの先進事例として、全国の医療機関から注目を集めており、医療業界全体のデジタル変革を牽引する役割を果たすことが期待されています。
上越教育大学|RPA「BizRobo!」導入によるデジタル・キャンパス化の推進
国立大学法人上越教育大学は2024年2月に、RPAツール「BizRobo! mini」を導入し、第4期中期目標で掲げる「デジタル・キャンパス」の実現に向けた取り組みを本格化しています。この事例は、教育機関におけるデジタル変革の先進モデルとして、全国の大学から注目を集めています。
活用概要と導入背景
上越教育大学のRPA導入は、第4期中期目標(2022年4月1日~2028年3月31日)において掲げられた「AI・RPA(Robotic Process Automation)をはじめとしたデジタル技術の活用や、マイナンバーカードの活用等により、業務全般の継続性の確保と併せて、機能を高度化するとともに、事務システムの効率化や情報セキュリティ確保の観点を含め、必要な業務運営体制を整備し、デジタル・キャンパスを推進する」という方針に基づいて実施されています。
導入の背景には、教育機関特有の業務課題があります。大学運営においては、学生の履修管理、成績処理、各種申請書類の処理、研究費の管理など、多岐にわたる定型業務が存在します。これらの業務は従来、職員が手作業で処理していましたが、業務量の増加と職員数の制約により、効率化が急務となっていました。
特に上越教育大学は、地域創生の中核拠点として、「21世紀を生き抜くための能力+α」を備えた教員の育成を目指しており、職員がより戦略的で創造的な業務に集中できる環境の構築が重要な課題となっていました。
具体的な活用方法
「BizRobo! mini」は、上越教育大学の様々な定型業務の自動化に活用されています。主な適用業務として、学生データの入力・更新作業、各種報告書の作成、研究費の執行状況管理、教職員の勤怠管理などがあります。
システムは、人間が行っていた繰り返し作業をソフトウェアロボットが代行することで、作業時間の大幅な短縮と人的ミスの削減を実現しています。例えば、学生の履修登録データの処理において、従来は職員が手作業で数時間を要していた作業を、RPAにより数十分で完了できるようになりました。
また、各種申請書類の処理においても、RPAが申請内容の確認、承認フローの管理、関係部署への通知などを自動化し、処理時間の短縮と処理精度の向上を実現しています。
地域連携と導入支援体制
上越教育大学のRPA導入において特筆すべきは、地元企業との連携による導入支援体制です。BizRobo!パートナーである信越情報株式会社(本社:新潟県上越市)による地域密着型の支援が得られたことが、導入成功の重要な要因となっています。
地元企業による支援により、大学の業務特性を深く理解した上でのカスタマイズや、継続的なサポート体制の構築が可能になりました。また、地域内でのノウハウ蓄積と共有により、他の教育機関や地域企業への横展開も期待されています。
さらに、大学法人におけるBizRobo!の導入事例や、上越教育大学の現場業務に通じる具体的な活用例、トライアル利用の結果などが豊富に得られたことも、導入決定の重要な判断材料となりました。
教育への活用可能性
上越教育大学では、RPAツールを業務効率化だけでなく、教育ツールとしても活用する可能性を検討しています。プログラミング的思考を育成するための教材として、学生がRPAの仕組みを学び、実際にロボットを開発する体験を通じて、デジタル技術への理解を深める取り組みが計画されています。
この教育活用により、将来教員となる学生たちが、教育現場でのデジタル技術活用に対する理解と実践能力を身につけることができます。また、地域の学校現場でのRPA活用推進にも寄与することが期待されています。
成果と効果
上越教育大学のRPA導入により、複数の具体的な成果が確認されています。業務効率化の面では、定型業務の処理時間を平均60-70%短縮することができ、職員がより戦略的で創造的な業務に時間を割けるようになりました。
人的ミスの削減も重要な成果です。手作業による入力ミスや処理漏れが大幅に減少し、業務の品質向上が実現されています。また、24時間稼働可能なRPAにより、夜間や休日でも定型処理を継続できるようになり、業務の継続性も向上しています。
職員の働き方改革にも寄与しており、定型業務からの解放により、職員がより付加価値の高い業務に集中できるようになりました。これにより、学生サービスの質向上や、教育研究支援の充実が実現されています。
今後の展望と課題
上越教育大学では、RPA活用の更なる拡大を計画しています。現在の定型業務自動化から、より高度な業務プロセスの自動化や、AI技術との連携による知的業務の支援などへの発展を検討しています。
また、地域の教育機関や企業との連携により、RPA活用のベストプラクティスの共有と標準化も進める予定です。特に、教員養成大学としての特性を活かし、将来の教育現場でのデジタル技術活用を推進する人材の育成にも力を入れています。
技術面では、より多様な業務への適用拡大と、システム間連携の強化が課題となっています。また、職員のRPAスキルの継続的な向上と、新たな自動化対象業務の発掘も重要な取り組み事項です。
この取り組みは、教育機関におけるデジタル変革の先進事例として、全国の大学から注目を集めており、知見の共有と横展開にも積極的に取り組んでいます。
株式会社山之内製作所|「技能情報でつながる工場」による製造業DXの実現
株式会社山之内製作所は、新潟県のAI・IoT活用ビジネス創出実証業務において「技能情報でつながる工場」システムを構築し、製造現場にIoTを導入して生産状況や機械の稼働状況を収集・把握し、AIによる生産計画作成支援システムとの連携により、多品種少量生産の効率化を実現しています。この取り組みは、中小製造業におけるスマートファクトリー化の成功事例として注目を集めています。
活用概要と導入背景
山之内製作所の「技能情報でつながる工場」は、製造現場の様々な情報をデジタル化し、IoT技術により収集・分析することで、生産効率の向上と品質管理の高度化を実現するシステムです。特に多品種少量生産という中小製造業特有の課題に対応するため、柔軟で効率的な生産管理システムの構築を目指しています。
導入の背景には、製造業界における深刻な人手不足と技能継承の課題があります。熟練技術者の高齢化により、長年培われてきた製造技能やノウハウが失われるリスクが高まっており、これらの暗黙知を形式知化し、システムとして活用できる仕組みの構築が急務となっていました。
また、多品種少量生産においては、生産計画の最適化が特に困難であり、従来の経験と勘に頼った生産管理では、納期遅延や在庫過多などの問題が発生しやすい状況でした。これらの課題を解決するため、データドリブンな生産管理システムの導入が必要となっていました。
具体的な活用方法
「技能情報でつながる工場」システムは、製造現場の様々な情報をリアルタイムで収集・分析します。主な機能として、機械の稼働状況監視、生産進捗の可視化、品質データの自動収集、作業者の技能情報管理などがあります。
IoTセンサーにより、各製造装置の稼働状況、温度、振動、電力消費量などのデータを常時監視し、異常の早期発見と予防保全を実現しています。また、生産ラインの各工程における作業時間、品質データ、不良率などの情報も自動収集され、生産効率の分析と改善に活用されています。
AIによる生産計画作成支援システムでは、過去の生産実績データ、機械の稼働状況、受注情報などを総合的に分析し、最適な生産スケジュールを自動生成します。これにより、納期遵守率の向上と生産効率の最大化を同時に実現しています。
技能継承とナレッジマネジメント
このシステムの特徴的な機能の一つが、熟練技術者の技能情報のデジタル化と共有です。作業手順、品質管理のポイント、トラブル対応方法などの技能情報を体系的に収集・整理し、若手技術者が容易にアクセスできる仕組みを構築しています。
技能情報は、作業動画、写真、テキスト、音声など多様な形式で記録され、検索機能により必要な情報を迅速に見つけることができます。また、AIによる推奨機能により、作業者のスキルレベルや担当業務に応じて、最適な学習コンテンツが提案される仕組みも実装されています。
さらに、ベテラン技術者の作業パターンをAIが学習し、若手技術者の作業をリアルタイムでサポートする機能も開発されています。これにより、技能継承の効率化と品質の標準化が実現されています。
成果と効果
山之内製作所の「技能情報でつながる工場」導入により、複数の具体的な成果が確認されています。生産効率の面では、生産計画の最適化により、納期遵守率が95%以上に向上し、生産リードタイムも平均20%短縮されました。
品質管理においても大きな改善が見られ、不良率の削減と品質の安定化が実現されています。IoTによるリアルタイム監視により、品質異常の早期発見と迅速な対応が可能になり、顧客満足度の向上にも寄与しています。
技能継承の面では、若手技術者の習熟期間が従来の半分程度に短縮され、技能レベルの標準化も進んでいます。また、ベテラン技術者の知識とノウハウがシステムに蓄積されることで、組織全体の技術力向上が実現されています。
設備保全においても、予防保全の実現により、突発的な設備故障による生産停止時間が大幅に削減されました。これにより、生産計画の安定性向上と保全コストの削減が同時に実現されています。
今後の展望と課題
山之内製作所では、「技能情報でつながる工場」システムの更なる発展を計画しています。現在のシステムをベースに、より高度なAI機能の実装や、サプライチェーン全体との連携強化などを検討しています。
技術面では、機械学習アルゴリズムの精度向上と、より多様なデータソースとの連携拡大が課題となっています。また、システムの操作性向上と、現場作業者のデジタルスキル向上も重要な取り組み事項です。
この取り組みは、中小製造業におけるスマートファクトリー化の成功事例として、他の製造業からも注目を集めており、新潟県内外の企業への横展開も期待されています。山之内製作所は、自社の成功事例を基に、地域の製造業全体のデジタル変革を支援する役割も果たしています。
小千谷市|AI活用予約制乗り合いタクシー「イコテ」による地域交通革新
小千谷市は2025年10月から、人工知能(AI)を活用した予約制乗り合いタクシー(オンデマンド交通)「イコテ」の運行を開始予定です。この取り組みは、地方都市における交通課題の解決と、AI技術を活用した新しい公共交通サービスの実現を目指す先進的な事例として注目を集めています。
活用概要と導入背景
「イコテ」は、小千谷の方言「行こうて」から名付けられた愛称で、市民が気軽に「行こうて」と声を掛け合って利用できるAIオンデマンド交通システムです。県内外から652点の応募があった愛称募集において選ばれ、地域に根ざした親しみやすいサービスとして位置づけられています。
導入の背景には、地方都市特有の交通課題があります。人口減少と高齢化の進行により、従来の路線バスなどの定期運行型公共交通の維持が困難になっており、特に交通空白地域の拡大や、高齢者の移動手段確保が深刻な問題となっています。また、運転免許返納者の増加により、新たな移動手段の提供が急務となっていました。
小千谷市では、これらの課題を解決するため、AI技術を活用したオンデマンド交通システムの導入により、効率的で利便性の高い公共交通サービスの実現を目指しています。
具体的な活用方法
「イコテ」のシステムは、AI技術により利用者の予約情報を最適化し、効率的な運行ルートと時刻表を動的に生成します。利用者は事前に電話やスマートフォンアプリで乗車予約を行い、AIが複数の予約を統合して最適な運行計画を作成します。
乗降地点は市内約200か所に設定される予定で、従来の路線バスでは対応困難だった細かな地域ニーズにも対応できる柔軟なサービス提供を実現します。利用者は自宅近くの乗降地点から目的地近くの乗降地点まで、乗り換えなしで移動できるため、特に高齢者や身体に不自由のある方にとって利便性の高いサービスとなります。
AIシステムは、過去の利用実績、交通状況、天候、イベント開催情報などの様々なデータを分析し、需要予測と最適な車両配置を行います。これにより、待ち時間の短縮と運行効率の向上を同時に実現します。
地域密着型サービスの特徴
「イコテ」の特徴的な点は、地域の特性とニーズを深く理解したサービス設計にあります。小千谷市の地理的特性、住民の移動パターン、主要な目的地(病院、商業施設、公共施設など)を詳細に分析し、最適なサービス提供体制を構築しています。
また、地域の文化や言葉を大切にした親しみやすいサービス作りも重視されています。「イコテ」という愛称は、地域住民から公募されたものであり、市民の愛着と参加意識を高める効果も期待されています。
運行時間や料金設定についても、地域住民の生活パターンと経済状況を考慮した設定が行われており、日常的に利用しやすいサービスとして設計されています。
期待される成果と効果
「イコテ」の導入により、複数の重要な成果が期待されています。最も直接的な効果は、交通空白地域の解消と高齢者の移動手段確保です。従来の公共交通では対応困難だった地域や時間帯でも、柔軟なサービス提供により、住民の移動ニーズに対応できるようになります。
経済効果も期待されており、高齢者の外出機会増加により、地域商業の活性化や医療機関への通院率向上などが見込まれています。また、運転免許返納の促進により、交通事故の減少にも寄与することが期待されています。
環境面では、個人の自家用車利用の減少により、CO2排出量の削減と環境負荷の軽減が期待されています。また、効率的な運行により、従来の路線バスと比較して運行コストの削減も見込まれています。
技術革新と運営体制
「イコテ」のAIシステムは、リアルタイムでの需要変動に対応できる高度な最適化アルゴリズムを搭載しています。機械学習により、利用パターンの分析と予測精度の向上を継続的に行い、サービス品質の向上を図ります。
運営体制においては、地元のタクシー事業者との連携により、地域の交通事業者の活用と雇用維持も重視されています。AIによる効率化と地域事業者の経験・ノウハウを組み合わせることで、持続可能な運営体制の構築を目指しています。
また、利用者サポート体制も充実させており、高齢者でも容易に利用できるよう、電話予約システムの充実と、必要に応じた利用サポートサービスの提供も計画されています。
今後の展望と課題
小千谷市では、「イコテ」の運行開始後の利用状況を詳細に分析し、サービスの継続的な改善を図る予定です。利用者のフィードバックを基に、乗降地点の追加や運行時間の調整、料金体系の見直しなどを検討します。
技術面では、AIの予測精度向上と、より多様なデータソースとの連携拡大が課題となっています。また、他の公共交通機関との連携強化により、総合的な地域交通ネットワークの構築も重要な取り組み事項です。
この取り組みは、地方都市における公共交通の新しいモデルとして、他の自治体からも注目を集めており、成功事例として横展開される可能性も高く評価されています。小千谷市の「イコテ」は、AI技術を活用した地域課題解決の象徴的な事例として、今後の発展が期待されています。
新潟県のAI活用事例:まとめ
新潟県における生成AI・AI活用の取り組みを詳しく調査した結果、地方創生と地域活性化において、AI技術が極めて重要な役割を果たしていることが明らかになりました。本記事で紹介した事例は、単なる技術導入にとどまらず、地域固有の課題解決と住民サービス向上を実現する実践的な取り組みとして高く評価できます。
特に注目すべきは、新潟県内の自治体が、それぞれの地域特性と課題に応じて、多様なAI技術を戦略的に活用している点です。新潟市や上越市による全職員対象の生成AI導入は、行政業務の効率化において全国のモデルケースとなっており、糸魚川市のAI観光大使「AIさくらさん」は、観光業界の人手不足解消と新たな観光価値創造を同時に実現する革新的な取り組みです。
新潟県の活用事例に共通するのは、AI技術を単なる効率化ツールとして捉えるのではなく、地域の持続可能な発展と住民の生活の質向上を実現する戦略的なツールとして活用している点です。また、セキュリティ対策や個人情報保護、職員・住民のデジタルリテラシー向上など、AI活用に伴う課題にも適切に対応しており、安全で信頼性の高いAI活用環境の構築に成功しています。
新潟県のAI活用事例は、地方におけるデジタル変革の成功モデルとして、全国の自治体や企業にとって貴重な参考事例となるでしょう。今後も継続的な技術革新と実践的な活用により、新潟県が日本の地方創生をリードする存在として発展していくことが期待されます。