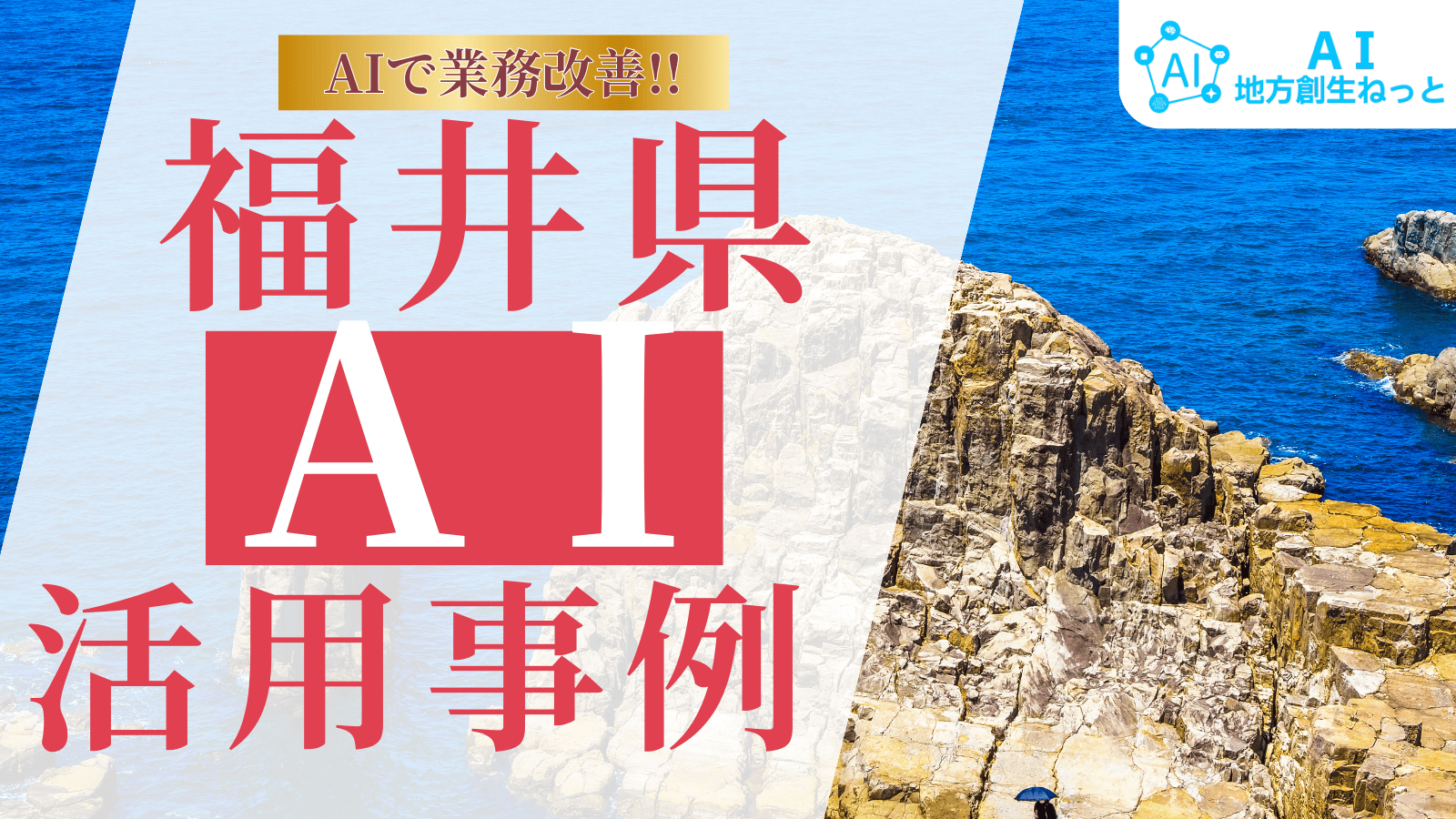福井県は、この生成AI活用において全国でも先進的な取り組みを展開している地域の一つです。県庁をはじめとする自治体での全庁導入、教育機関での実践的な研究活用、医療機関での患者サービス向上、そして民間企業での業務効率化まで、幅広い分野で具体的な成果を上げています。
本記事では、福井県内の自治体、学校法人、病院、民間企業における生成AI活用の具体的な事例を詳しく紹介し、それぞれの活用方法、導入プロセス、得られた成果について詳細に解説します。

水野倫太郎
(株)ICHIZEN HOLDINGS
代表取締役
慶應義塾大学経済学部卒。2017年米国留学時ブロックチェーンと出会う。2018年仮想通貨メディアCoinOtaku入社。2019年同社のCMO就任、2020年に東証二部上場企業とM&A。2022年(株)ICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ、Web3事業のコンサルティングをNTTをはじめとした大企業から海外プロジェクト、地方自治体へ行う。ブロックチェーンだけでなく生成AI導入による業務効率化を自治体中心に支援中。

監修 水野倫太郎
(株)ICHIZEN HOLDINGS
代表取締役
慶應義塾大学経済学部卒。2017年米国留学時ブロックチェーンと出会う。2018年仮想通貨メディアCoinOtaku入社。2019年同社のCMO就任、2020年に東証二部上場企業とM&A。2022年(株)ICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ、Web3事業のコンサルティングをNTTをはじめとした大企業から海外プロジェクト、地方自治体へ行う。ブロックチェーンだけでなく生成AI導入による業務効率化を自治体中心に支援中。
福井県庁|全国トップクラスの生成AI全庁導入による業務革新
活用事例の概要
福井県庁は、2023年6月から生成AIの実証実験を開始し、2024年4月には全庁での本格導入を実現しました。使用しているのはエクサウィザーズが提供する「exaBase 生成AI」で、全職員を対象とした包括的な活用体制を構築しています。この取り組みは、地方自治体における生成AI活用の先進事例として全国から注目を集めています。
実証実験の結果、約95%の職員が「生産性向上に寄与する」と評価し、具体的な業務時間の短縮効果も数値で実証されています。福井県の取り組みが特筆すべき点は、単なる技術導入にとどまらず、職員の業務プロセス改善と組織全体の効率化を同時に実現していることです。
活用方法
福井県庁では、生成AIを以下の3つの主要な分野で活用しています。
政策立案支援での活用 水素需要喚起施策のアイデア出しにおいて、生成AIを活用した事例では、職員が思いつかないような多角的な提案を得ることができました。従来であれば4人のグループで30分かけて行っていたブレインストーミングが、生成AIとの対話により5分で完了し、115分もの時間短縮を実現しています。AIが提案した10個のアイデアは、あらゆる角度からの提案を含んでおり、検討の幅を大幅に広げることができました。
事業企画・開発での活用 伝統野菜関係の事業において、生産者の現状や要望を踏まえた施策案の作成に生成AIを活用しています。AIが提案するアイデアは一般的な内容であっても、体系的に整理されており、キーワードを拾って詳細を調べやすい形で提示されるため、施策案としてまとめやすくなっています。従来は一人で数日かけて悶々と考えていた作業が、AIとのブレインストーミングにより30分で完了するようになりました。
技術的課題解決での活用 道路舗装の補修工事に関するブレインストーミングでは、現場条件を与えることで最適な補修方法の選定を支援しています。生成AIは提案だけでなく、その提案の利点・欠点の補足説明も行ってくれるため、職員が気づかなかった観点を整理でき、明確な結論を導き出すことができています。
成果
福井県庁の生成AI活用による成果は、定量的・定性的両面で明確に現れています。
時間短縮効果 最も顕著な成果は業務時間の大幅な短縮です。道路舗装補修工事の事例では、従来3人×30分の施工方法決定、2時間の計画書作成、30分×2回の協議資料作成で計4.5時間かかっていた作業が、1時間未満で完了するようになりました。これは約78%の時間短縮に相当し、職員がより付加価値の高い業務に集中できる環境を創出しています。
業務品質の向上 生成AIの活用により、職員個人の経験や知識に依存していた業務プロセスが標準化され、一定の品質を保った成果物を効率的に作成できるようになりました。特に政策立案の場面では、AIが多角的な視点を提供することで、従来では見落としがちだった観点を含む包括的な検討が可能になっています。
職員の意識変革 約95%の職員が生産性向上を実感していることは、単なる技術導入を超えた組織文化の変革を示しています。職員がAIを「業務パートナー」として認識し、創造的な業務により多くの時間を割けるようになったことで、仕事に対するモチベーションの向上も報告されています。
福井県庁の事例は、生成AIが地方自治体の業務効率化だけでなく、職員の働き方改革や組織全体のイノベーション創出にも寄与することを実証した貴重な事例といえるでしょう。
越前市|県内初のChatGPT導入で実現した大幅な業務効率化
活用事例の概要
越前市は、2023年5月に福井県内の自治体として初めて生成AIを業務に試験導入した先駆的な自治体です。ChatGPTを市専用のクラウド環境で運用し、2023年5月から10月までの検証期間中に、職員522人による計3,457件の活用事例を蓄積しました。この取り組みは、地方自治体における生成AI活用のパイオニア的存在として、他の自治体からも注目を集めています。
越前市の特徴は、単なる技術導入ではなく、市が定める各種計画や例規などの情報に基づいて質問に回答するシステムを構築したことです。これにより、職員が日常業務で必要とする情報に迅速にアクセスできる環境を整備し、業務効率化と質の向上を同時に実現しています。
活用方法
越前市では、生成AIを以下の主要な業務分野で活用しています。
文書作成業務の効率化 市の各種計画書や報告書の作成において、生成AIが下書きや構成案を提供することで、職員の文書作成時間を大幅に短縮しています。特に定型的な文書については、AIが作成した標準的な内容に職員が必要な情報を追記することで、品質を保ちながら効率的に完成させることができています。あいさつ文の作成では、AIが生成した標準的な内容をベースに、職員が状況に応じてカスタマイズを加える手法が定着しています。
企画立案支援 新しい施策や事業の企画立案において、生成AIがアイデア出しや課題整理を支援しています。職員が抱える課題や目標をAIに入力することで、多角的な視点からの提案や類似事例の紹介を受けることができ、企画の質向上と検討時間の短縮を両立しています。
市民対応業務の支援 高齢者福祉など複雑な制度について、市民向けに分かりやすく説明する資料の作成にAIを活用しています。専門的な内容を一般市民にも理解しやすい表現に変換する作業において、AIの自然言語処理能力が大きな効果を発揮しています。
情報検索・要約業務 市総合計画などの長大な文書の要約や、特定の情報の検索において、AIが迅速かつ正確な結果を提供しています。職員は「いつでも何回でも気兼ねなく質問できる」環境を得ることで、業務に必要な情報へのアクセス性が飛躍的に向上しています。
成果
越前市の生成AI活用は、具体的で測定可能な成果を上げています。
定量的成果 最も注目すべき成果は、職員1人当たり年間60時間の削減効果です。これは月平均5時間の業務時間短縮に相当し、職員がより創造的で付加価値の高い業務に集中できる時間を創出しています。検証期間中の活用事例3,457件という数字は、職員の積極的な活用姿勢と、システムの実用性の高さを物語っています。
定性的成果 職員アンケートでは、77%が「業務の質が向上する」と回答しており、単なる効率化を超えた質的改善も実現されています。特に以下の点で顕著な改善が見られています。
長文書類の理解促進において、市総合計画などの複雑な文書をAIが要約することで、職員がポイントを迅速に把握できるようになりました。これにより、政策の一貫性確保や関連部署間の連携強化が図られています。
文書作成の標準化が進み、部署や職員による品質のばらつきが減少しています。AIが提供する標準的な構成や表現をベースとすることで、市民に対してより統一感のある情報提供が可能になっています。
今後の展開と課題 越前市では、検証結果を踏まえて2024年度の本格導入を目指しており、別仕様の製品による導入も検討しています。また、AIへの効果的な指示文(プロンプト)作成に関する職員研修にも力を入れており、活用スキルの底上げを図っています。
一方で、住民向けサービスについては、検証結果で正確な回答の割合が58%にとどまったため、現時点での導入は見送り、今後の技術革新を注視する方針です。この慎重なアプローチは、市民サービスの質を最優先に考える越前市の姿勢を示しています。
越前市の事例は、地方自治体が生成AIを段階的かつ戦略的に導入することで、職員の業務効率化と市民サービスの質向上を両立できることを実証した貴重な事例です。
敦賀市|Z-SCHOOLで実現する次世代人材育成と地域課題解決
活用事例の概要
敦賀市は、2024年度に「Z-SCHOOL」という中高生向け生成AI教育プログラムを初実施し、教育分野における生成AI活用の先進的な取り組みを展開しています。このプログラムは「AI×クリエイティブ」をテーマに、市内在住の中学生・高校生を対象として8か月間のオンラインプログラムを実施し、生成AIを活用した地域課題解決に取り組んでいます。
参加者は中学生5名、高校生14名の計19名で、全員が8か月間のプログラムを完走しました。このプログラムの特徴は、単なる技術習得にとどまらず、参加者が実際に地域の課題を発見し、生成AIを活用してその解決策を具体的なプロダクトとして形にすることです。敦賀市の取り組みは、地方自治体が次世代人材育成と地域活性化を同時に推進する革新的なモデルとして注目されています。
活用方法
Z-SCHOOLでは、参加者が以下のプロセスで生成AIを活用した地域課題解決に取り組んでいます。
地域課題の発見と分析 参加者はまず、敦賀市が抱える様々な課題を自分たちの視点で発見し、分析することから始めます。観光振興、移住促進、商店街活性化など、中高生ならではの視点で地域の課題を捉え、それらを解決するためのアプローチを検討します。この段階で、生成AIを活用して課題の多角的な分析や類似事例の調査を行います。
プロダクト企画・設計 発見した課題に対して、生成AIを活用した解決策を具体的なWebサービスやアプリケーションとして企画・設計します。参加者は、ユーザーのニーズ分析、機能設計、ユーザーインターフェース設計などの工程で、生成AIの支援を受けながら実践的なプロダクト開発スキルを習得します。
実装・開発 企画したプロダクトを実際に開発する段階では、生成AIを活用してコーディング支援、デザイン作成、コンテンツ生成などを行います。参加者は技術的な知識が限られていても、AIの支援により本格的なWebサービスを構築することができています。
成果
Z-SCHOOLの成果は、参加者が作成した具体的なプロダクトと、彼らの成長に明確に現れています。
具体的な成果物
外国人観光客向けchatbot(角鹿中学校生徒作成) 敦賀市を訪れる外国人観光客が、言語の壁を越えて地元の美味しいレストランを自分自身で発見できるチャットボットを開発しました。このシステムは、観光客の好みや予算、立地条件などを聞き取り、最適なレストランを推薦する機能を持っています。生成AIを活用することで、多言語対応と個人の嗜好に合わせたパーソナライズされた推薦が可能になっています。
移住者向けchatbot(敦賀高校生徒作成) 敦賀市への移住を検討している人々が、移住前に知りたい情報を24時間いつでも質問できるチャットボットを開発しました。住居、仕事、教育、医療、生活環境など、移住に関する幅広い質問に対応し、移住希望者の不安解消と意思決定支援を行います。このシステムは、移住促進という敦賀市の重要な政策課題に直接貢献する実用的なソリューションとなっています。
商店街活性化アプリ(敦賀工業高校生徒作成) 敦賀市の商店街を若い世代にも魅力的なお出かけスポットとして認知してもらうため、画像生成ガチャアプリを開発しました。このアプリは、商店街の各店舗の魅力を生成AIで作成した画像とともに紹介し、ゲーム要素を取り入れることで楽しみながら商店街を探索できる仕組みを提供しています。
教育的成果 参加者は8か月間のプログラムを通じて、技術スキルだけでなく、課題発見能力、企画力、実行力、プレゼンテーション能力など、総合的な能力を向上させています。特に重要なのは、地域課題を自分事として捉え、その解決に向けて主体的に行動する姿勢を身につけたことです。
また、他地域の同学年との交流を通じて、敦賀市以外の地域課題や解決アプローチを学ぶ機会も得ており、より広い視野での課題解決能力を養っています。プログラム修了後は、指導者として後輩の育成に携わることが期待されており、持続可能な人材育成サイクルの構築を目指しています。
今後の展開 敦賀市では、Z-SCHOOLの成果を踏まえて、小学生から高校生までの切れ目ない「ステップアップ型のデジタル教育」を展開する予定です。この取り組みにより、長期的な視点で地域のデジタル人材を育成し、将来的な地域活性化の担い手を確保することを目指しています。
敦賀市のZ-SCHOOLは、生成AIを活用した教育プログラムが、次世代人材育成と地域課題解決を同時に実現できることを実証した画期的な事例です。
福井工業大学|6万件の観光データを活用した生成AI地域観光DX
活用事例の概要
福井工業大学AI&IoTセンターの芥子育雄教授の研究室では、福井県の観光客から収集した過去3年間で約6万件という膨大なアンケートデータを活用し、生成AIとGoogle Cloudを組み合わせた地域観光DXプロジェクトを推進しています。このプロジェクトは、単なる学術研究にとどまらず、実際の観光事業者や地域経済への具体的な貢献を目指した実践的な取り組みとして注目されています。
プロジェクトの特徴は、構造化・非構造化データを横断的に分析し、観光客一人ひとりの興味や属性に合わせたパーソナライズされた情報提供を実現することです。また、分析結果を観光事業者にフィードバックすることで、観光資源の最適化と地域全体の観光競争力向上を図っています。研究室の学生が主体となって進めるこのプロジェクトは、産学連携による地域貢献の優れたモデルケースとなっています。
活用方法
福井工業大学では、生成AIを以下の段階的なアプローチで地域観光DXに活用しています。
データ収集・蓄積・分析基盤の構築 Google Cloudをデータの収集・蓄積・分析基盤として活用し、福井県内の観光地で収集された約6万件のアンケートデータを体系的に管理しています。このデータには、観光客の属性情報、訪問目的、満足度、消費行動、再訪意向など、観光行動に関する多様な情報が含まれています。生成AIは、これらの膨大なデータから有意義なパターンや傾向を抽出し、観光客の行動予測や嗜好分析を行います。
パーソナライズされた情報提供システム 生成AIを活用して、観光客一人ひとりの興味や属性に合わせたパーソナライズされた観光情報を提供するシステムを開発しています。観光客の過去の行動データや表明された嗜好を分析し、最適な観光ルート、レストラン、宿泊施設、体験プログラムなどを推薦します。このシステムにより、観光客の満足度向上と滞在時間延長、消費額増加を目指しています。
観光事業者向けフィードバックシステム 分析結果を観光事業者に対して具体的なアドバイスとして提供するシステムも構築しています。どのような属性の観光客がどの時期に何を求めているか、競合他地域と比較した福井県の強みや改善点は何かなど、事業戦略立案に直接活用できる情報を提供しています。
学生主体の実践的プロジェクト運営 このプロジェクトでは、研究室の学生が主体となって実際のデータ分析、システム開発、成果発表を行っています。学生たちは生成AIツールの操作方法を習得するだけでなく、実際のビジネス課題に対してAIを活用した解決策を提案する経験を積んでいます。これにより、理論と実践を結びつけた実践的なAI活用スキルを身につけています。
成果
福井工業大学の地域観光DXプロジェクトは、複数の側面で具体的な成果を上げています。
観光DXの推進 6万件という大規模なデータセットを活用することで、従来では不可能だった詳細な観光客行動分析が可能になりました。季節別、属性別、目的別の観光客の嗜好や行動パターンが明確になり、より効果的な観光施策の立案が可能になっています。特に、観光客の潜在的なニーズや未開拓の観光資源の発見において、AIの分析能力が大きな効果を発揮しています。
地域貢献の実現 分析結果は実際の観光事業者や自治体の施策立案に活用されており、学術研究が直接的に地域経済に貢献する仕組みが構築されています。観光ルートの最適化、プロモーション戦略の改善、新たな観光商品の開発など、具体的な事業改善につながる提案が行われています。
学生の実践的AI活用スキル習得 参加学生は、単なる技術習得を超えて、実際のビジネス課題に対してAIを活用した解決策を提案する能力を身につけています。データ分析、システム設計、プレゼンテーション、ステークホルダーとのコミュニケーションなど、AI時代に求められる総合的なスキルを実践的な環境で習得しています。
産学連携モデルの確立 クラウドエースとの連携により、最新のクラウド技術と生成AI技術を組み合わせた実践的なプロジェクトが実現されています。企業の技術力と大学の研究力、学生の創造力を組み合わせることで、単独では実現困難な大規模プロジェクトを成功させています。
今後の展望 このプロジェクトは、福井県の観光DXのさらなる発展を目指して継続的に拡張される予定です。リアルタイムデータの活用、他地域との比較分析、インバウンド観光客への対応強化など、より高度な分析と提案を行う計画が進められています。
福井工業大学の事例は、大学の研究活動が地域の実際の課題解決に直接貢献し、同時に学生の実践的教育も実現する、産学連携による地域貢献の理想的なモデルを示しています。
福井県済生会病院|がん患者に寄り添う対話型AIケアボットの実証実験
活用事例の概要
福井県済生会病院は、福井工業大学AI&IoTセンターとの共同研究により、がん患者さんの支援を目的とした対話型AIケアボットの実証実験を実施しています。この取り組みは、生成AIとLive2D女性医師キャラクターを組み合わせた革新的なシステムで、医療現場における患者ケアの新たな可能性を探る先進的な実証実験として注目されています。
2024年12月9日と12月13日に実施された実証実験では、60歳未満から90代までの幅広い年齢層のがん患者10名が参加し、AIケアボットとの30分間の対話を行いました。この実験は、宗本義則副院長の立ち会いのもと、患者さんの安全と心理的サポートに十分な配慮をしながら進められており、医療現場でのAI活用における安全性と有効性の両立を重視したアプローチが取られています。
活用方法
福井県済生会病院では、AIケアボットを以下の方法で患者ケアに活用しています。
対話型患者状態評価システム AIケアボットは、がん患者さんとの自然な対話を通じて、患者の身体的・精神的状態を評価するシステムとして機能しています。Live2D技術により人間らしい外見を持つ女性医師キャラクターが、患者さんに親しみやすい環境で対話を行います。AIは患者さんの発言内容、話し方、表情などから、痛みの程度、不安レベル、治療への理解度、家族関係などを総合的に分析し、医療スタッフでは気づきにくい微細な変化も捉えることができます。
24時間対応の相談窓口機能 従来の医療現場では、患者さんが医師や看護師に相談できる時間は限られていましたが、AIケアボットは24時間いつでも患者さんの相談に応じることができます。夜間や休日に不安を感じた患者さんが、気軽に相談できる環境を提供することで、患者さんの心理的負担の軽減を図っています。AIは患者さんの質問に対して適切な情報提供を行うとともに、緊急性の高い症状や状況を検知した場合には、適切な医療スタッフへの連絡を促すアラート機能も備えています。
個別化されたケア提案 AIケアボットは、各患者さんの病状、治療経過、性格、家族構成などの個別情報を学習し、一人ひとりに最適化されたケア提案を行います。例えば、化学療法の副作用に悩む患者さんには具体的な対処法を提案し、治療への不安を抱える患者さんには励ましの言葉や成功事例の紹介を行います。このパーソナライズされたアプローチにより、画一的なケアでは対応困難な個別ニーズに応えることができています。
医療スタッフとの連携強化 AIケアボットが収集した患者情報は、医療スタッフと共有され、より包括的な患者ケアの実現に活用されています。患者さんがAIに話した内容から、医療スタッフが見落としがちな患者の心配事や要望を発見し、治療計画やケア方針の改善に反映させることができます。
成果
福井県済生会病院のAIケアボット実証実験は、医療現場でのAI活用において重要な成果を上げています。
患者状態評価の精度向上 実証実験の結果、AIによる対話を通じて患者さんの状態や緊急対応の必要性を評価できる可能性が確認されました。特に、患者さんが医療スタッフには言いにくい悩みや不安をAIには率直に話すケースが多く見られ、より正確な患者状態の把握が可能になっています。AIは感情的な判断に左右されることなく、客観的な基準で患者の状態を評価するため、見落としのリスクを減らすことができています。
医療サービスの質向上 AIケアボットが提供する24時間対応により、患者さんの不安や疑問に迅速に対応できるようになりました。これにより、患者満足度の向上と、医療スタッフの負担軽減を同時に実現しています。また、AIが収集した患者情報を活用することで、医療スタッフはより効率的で効果的な患者ケアを提供できるようになっています。
迅速な医療連携の実現 AIケアボットが患者の状態変化や緊急性の高い症状を早期に検知することで、適切な医療サービスや相談支援への迅速な連携が可能になっています。これにより、重篤な状態への進行を防ぎ、患者の安全性向上に貢献しています。
患者の心理的支援効果 多くの参加患者から、「AIだからこそ話しやすい」「人間の医師には遠慮してしまうことも気軽に相談できる」といった肯定的な反応が得られています。特に、Live2D技術による親しみやすいキャラクターデザインが、患者さんの心理的ハードルを下げる効果を発揮しています。
今後の展開 この実証実験の成果を踏まえ、福井県済生会病院では、AIケアボットのさらなる機能拡張と実用化を検討しています。他の診療科への展開、在宅療養患者への対応、家族向けサポート機能の追加など、より包括的な患者ケアシステムの構築を目指しています。
福井県済生会病院の事例は、生成AIが医療現場において患者ケアの質向上と医療スタッフの業務効率化を同時に実現できることを実証した画期的な取り組みです。
福井県内地元企業12社|THINK AIプロジェクトによる中小企業のAI活用推進
活用事例の概要
福井新聞社・電通・レッジが共同で開催した「THINK AI」プロジェクトは、福井県内の地元企業12社が参加し、中小企業におけるAI活用の可能性を探る画期的な取り組みです。参加企業は、クリーニング店、古紙回収企業など、多様な業種にわたる地域密着型の企業で構成されており、それぞれが自社でAIプロジェクトを立ち上げることを目標としています。
このプロジェクトの特徴は、ソニーネットワークコミュニケーションズが提供する予測分析ツール「Prediction One」を活用し、プログラミング知識がない企業でも実用的なAI活用を体験できる点です。7月、8月、9月の3回にわたるワークショップを通じて、参加企業は段階的にAI活用スキルを習得し、実際のビジネス課題に対するAIソリューションを検討しています。
活用方法
THINK AIプロジェクトでは、以下の段階的なアプローチでAI活用を推進しています。
DAY1:基礎理解と課題発見 最初のワークショップでは、AIの基礎理解セミナーと自社課題発見ワークショップを実施しました。参加企業は、AIがどのような課題を解決できるのか、自社の業務プロセスのどこにAI活用の余地があるのかを体系的に学習しました。各企業が抱える具体的な課題を明確化し、AI活用による解決可能性を検討するプロセスを通じて、実践的なAI導入計画の基礎を築きました。
DAY2:実践的AI体験 2回目のワークショップでは、Prediction Oneを用いた体験型ワークショップを実施しました。参加者は、「とある八百屋における、明日売れるトマトの売上予測」などの身近なテーマを使って、実際にデータをアップロードし、予測モデルを作成する体験を行いました。学習用と予測用のデータをcsv形式で提供し、参加者が精度に寄与しそうなカラムを選択してモデルを作成し、結果画面からカラムの寄与度や精度を確認するプロセスを繰り返すことで、AI活用の実際的な感覚を身につけました。
DAY3:プロジェクト案発表 最終回では、各企業が自社で行うAIプロジェクト案の発表を行いました。これまでのワークショップで習得した知識と体験を基に、実際のビジネス課題に対するAI活用提案を具体化し、他の参加企業や主催者からのフィードバックを受けることで、実現可能性の高いプロジェクト計画を策定しました。
成果
THINK AIプロジェクトは、参加企業にとって複数の重要な成果をもたらしています。
技術ハードルの大幅な低下 最も顕著な成果は、参加者にとってAIツール利用のハードルが大幅に下がったことです。従来、AI活用には高度な技術知識が必要と考えられていましたが、Prediction Oneのような直感的なツールを実際に操作することで、エンジニアでなくてもAIモデルを作成できることを実感しました。一度やり方を覚えてしまえば、同じ手法で別の予測分析を行うことも可能になり、実際に後日、自社データを活用して予測分析を行う参加者も現れています。
AI活用の勘所習得 参加者は、AIがどのような課題を解決可能で、どのような課題解決は苦手なのかという勘所を掴むことができました。予測分析の体験を通じて、データの質や量が結果に与える影響、適切な変数選択の重要性、結果の解釈方法などを実践的に学習しました。この経験により、自社の課題に対してAIが有効かどうかを適切に判断できるようになっています。
データ収集の重要性認識 ワークショップでは、サンプルデータを使用しましたが、参加者が自社で予測分析を行うためには、自社のデータを一定量整理した状態で準備する必要があることを実感しました。予測分析をするためにはどのようなデータが必要かという見立てを立てることができるようになり、データ収集の難しさとその重要性を自ら気づくことができました。
継続的な活用への発展 プロジェクト終了後も、複数の参加企業がPrediction Oneを使用して自社データを活用した予測分析を継続しています。売上予測、在庫最適化、顧客行動分析など、各企業の業種や課題に応じた多様な活用が展開されており、ワークショップが実際のビジネス改善につながっています。
福井県観光連盟|生成AIツール実証事業による観光業界のDX推進
活用事例の概要
福井県観光DXコンソーシアムが実施する「生成AIツール実証事業」は、県内の観光事業者や自治体職員を対象とした大規模な実証プロジェクトです。2025年9月16日から11月30日までの期間で、100名の参加者を募集し、観光業界における生成AI活用の可能性を探っています。この事業は、観光施設、宿泊施設、飲食店、道の駅などの観光事業者と、自治体およびDMO・観光協会職員が対象となっており、観光業界全体のデジタル変革を目指しています。
活用方法
福井県観光連盟では、生成AIを以下の2つの主要な方向で活用しています。
FTASデータの自動分析とレポート化 福井県観光データ活用プラットフォーム(FTAS)に公開されているオープンデータを生成AIで自動分析し、視認性の高い観光動向レポートを作成しています。従来は手動で時間をかけて行っていた複雑なデータ分析作業を、AIが自動化することで、誰でも手軽に観光動向を把握できるようになっています。また、必要な情報をプッシュ配信(通知)する機能により、観光事業者が最新の市場動向を迅速に把握し、適切な経営判断を行えるよう支援しています。
観光業務支援AI「mitsumonoAI」の提供 福井県観光DXコンソーシアムが開発した生成AIツール「mitsumonoAI」を提供し、観光事業者や自治体職員の日常業務を効率化しています。このツールは、「使えない」をゼロにすることを目標に設計されており、外部に頼らず自分たちでマーケティングができるよう支援しています。具体的には、観光プランの企画、プロモーション文章の作成、顧客対応の自動化、市場分析レポートの生成などの機能を提供しています。
成果
福井県観光連盟の生成AIツール実証事業は、観光業界のDX推進において重要な成果を期待しています。
業務効率化の実現 手動で時間をかけて行っていた分析の手間を大幅に削減し、観光事業者がより創造的で付加価値の高い業務に集中できる環境を創出しています。特に小規模な観光事業者にとって、専門的なデータ分析スキルがなくても高度な市場分析を行えることは、競争力向上に直結する重要な成果となっています。
マーケティング能力の向上 生成AIツールの活用により、観光事業者が外部のコンサルタントに依存することなく、自分たちでマーケティング活動を企画・実施できるようになっています。これにより、コスト削減と同時に、地域の特性を深く理解した効果的なマーケティング戦略の立案が可能になっています。
観光動向把握の民主化 従来は一部の専門家や大手事業者のみが行えていた高度な観光動向分析を、中小の観光事業者でも手軽に実施できるようになっています。これにより、データに基づいた意思決定が観光業界全体に普及し、より効果的な観光施策の立案と実行が期待されています。
福井県内の民間企業におけるこれらのAI活用事例は、中小企業でも適切な支援とツールがあれば、AI技術を効果的に活用できることを実証しています。
終わりに
福井県における生成AI活用の取り組みを詳しく調査した結果、地方自治体、教育機関、医療機関、民間企業のそれぞれが、地域の特性と課題に応じた独創的で実践的なAI活用を展開していることが明らかになりました。これらの事例は、生成AIが単なる技術的なツールにとどまらず、地方創生と地域活性化の強力な推進力となり得ることを実証しています。
特に注目すべきは、福井県の取り組みが「技術のための技術」ではなく、明確な課題解決と成果創出を目指した実用的なアプローチを取っていることです。福井県庁の全庁導入では具体的な時間削減効果を測定し、越前市では職員の77%が業務の質向上を実感し、敦賀市のZ-SCHOOLでは中高生が実際に地域課題を解決するプロダクトを開発しています。これらの成果は、生成AI活用が確実に地域の生産性向上と課題解決に貢献していることを示しています。
福井県の生成AI活用事例は、全国の自治体や企業にとって貴重な参考事例となるでしょう。特に、地方創生や地域活性化に取り組む関係者にとって、これらの事例は具体的な行動指針と成功への道筋を示すものです。生成AIという新しい技術を活用して、地域の課題を解決し、住民の生活の質を向上させ、地域経済を活性化させる福井県の取り組みは、日本の地方創生における新たなモデルケースとして、今後さらなる発展が期待されます。