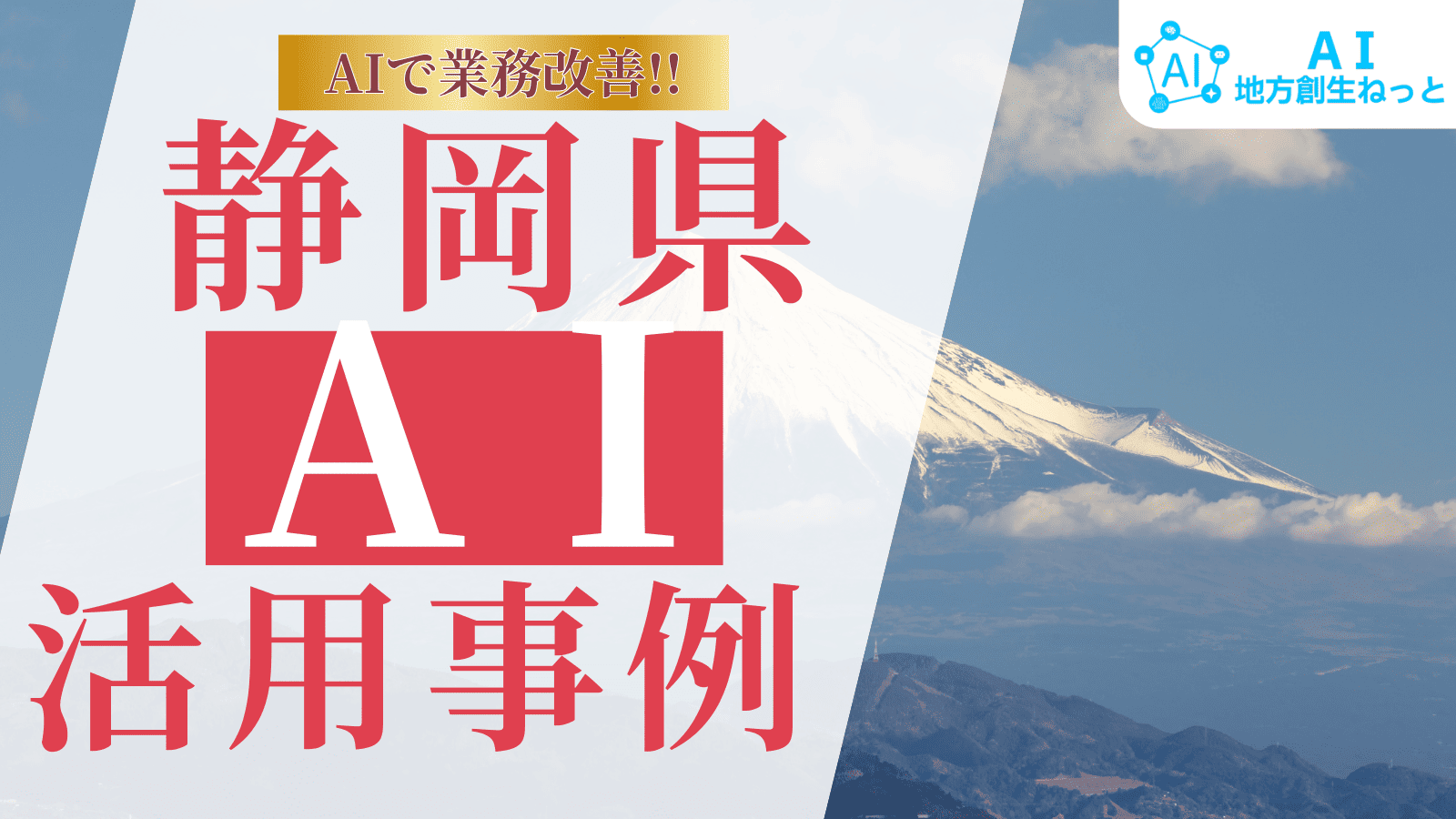近年、業務効率化や新たな価値創出の切り札として、生成AIをはじめとするAI技術が急速に普及しています。この流れは地方自治体や地域企業も例外ではなく、「幸福度日本一」を掲げる静岡県でも、行政サービスの向上や地域活性化に向けたユニークなAI活用が次々と始まっています。
この記事では、静岡県庁や県内市町といった自治体の先進的な取り組みから、地域のインフラや産業を支える企業、さらには教育・医療現場での活用まで、静岡県内で進む生成AI・AI活用の具体的な事例を詳しくご紹介します。自治体関係者の方、地域活性化に興味があるビジネス層の方、そしてAIの可能性に関心を持つすべての方にとって、参考になる情報が満載です。

水野倫太郎
(株)ICHIZEN HOLDINGS
代表取締役
慶應義塾大学経済学部卒。2017年米国留学時ブロックチェーンと出会う。2018年仮想通貨メディアCoinOtaku入社。2019年同社のCMO就任、2020年に東証二部上場企業とM&A。2022年(株)ICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ、Web3事業のコンサルティングをNTTをはじめとした大企業から海外プロジェクト、地方自治体へ行う。ブロックチェーンだけでなく生成AI導入による業務効率化を自治体中心に支援中。

監修 水野倫太郎
(株)ICHIZEN HOLDINGS
代表取締役
慶應義塾大学経済学部卒。2017年米国留学時ブロックチェーンと出会う。2018年仮想通貨メディアCoinOtaku入社。2019年同社のCMO就任、2020年に東証二部上場企業とM&A。2022年(株)ICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ、Web3事業のコンサルティングをNTTをはじめとした大企業から海外プロジェクト、地方自治体へ行う。ブロックチェーンだけでなく生成AI導入による業務効率化を自治体中心に支援中。
静岡県庁の生成AI活用事例
全庁での生成AI導入による業務効率化
静岡県庁は2024年12月、エクサウィザーズ社が提供する自治体向け生成AIサービス「exaBase 生成AI for 自治体」を本庁の全職員約5,000人を対象に導入しました。
活用方法: このサービスの大きな特徴は、庁内の各種マニュアルや過去の資料といった独自データを連携できるRAG(検索拡張生成)技術に対応している点です。これにより、職員は以下のような多様な業務でAIを活用できます。
- 問い合わせ対応: 膨大な量のマニュアルを読み解かなくても、AIに質問するだけで関連情報を含んだ回答案を得られる。
- 資料作成・要約: 議会答弁のたたき台作成、FAQの作成、SNSの投稿文案作成など。
- 校正・評価: 作成した文章の誤字脱字チェックや、予算要求資料の評価・審査。
- データ分析: 地域の幸福度(Well-Being)に関する主観データと客観データの関係性分析。
成果: 導入に先立つ検証フェーズでは、資料の検索、要約、文章作成にかかる時間を大幅に削減できることが実証されました。 全庁展開により、職員一人ひとりの生産性を高め、より創造的な業務に時間を充てることで、県民サービスのさらなる向上を目指しています。
広報業務を効率化する画像生成AIの活用
県庁の広聴広報課では、SNSやウェブサイトで使用するバナー画像などの作成業務に、AIとプロのデザイナーが連携するユニークなサービスを導入しています。
活用方法: 職員が専用のフォームに、作成したい画像に関する説明文やキーワード、希望する色味などを入力するだけで、AIがデザイン案を自動で生成。その後、プロのデザイナーが微調整を加えることで、高品質な広報物が完成します。実際に、県のホームページに掲載されている「県政世論調査」のバナー作成などで活用されています。
成果: このサービスの導入により、従来1時間程度かかっていた画像作成の時間が最短20分にまで短縮されました。 デザインスキルに自信がない職員でも、質の高い画像をスピーディに作成できるため、情報発信の量とスピードが向上。利用した職員からは「大変役に立った」という声が多数寄せられており、業務負担の軽減と広報の質向上を両立しています。
県内産業を支える中小企業へのAI導入支援
静岡県は、自らの業務効率化だけでなく、県内経済の根幹をなす中小企業のデジタル化支援にも力を入れています。
活用方法: 産学官連携の「静岡県AI・IoT導入推進コンソーシアム」を設立し、専門家による技術支援や伴走支援を実施。また、静岡大学と連携した「IoT大学連携講座」などを開催し、中小企業がスモールスタートでAI・IoT活用を始められるよう、人材育成の面からもサポートしています。
成果: これらの取り組みを通じて、県内企業の生産性向上と競争力強化を後押しし、デジタル技術を駆使した持続可能な産業活動の実現を目指しています。
藤枝市の生成AI活用事例:無料ツールを活用した実証実験で業務改善意識を醸成
人口減少が進む中、限られた人員で質の高い市民サービスを維持するため、藤枝市では2024年11月から生成AIの活用をスタートしました。
活用方法: 導入のハードルを下げるため、100アカウントまで無償で利用できるコモンズAI社の「QommonsAI」を選定。まずは実証実験として、広報業務における資料作成や文章の要約といった、効果を実感しやすい業務から活用を進めています。
成果: 導入から間もないながら、研修に参加した職員からは「AIでこんなに業務が効率化できるなんて、目からウロコだった」といった前向きな声が上がっています。 AIの導入自体が、職員一人ひとりが主体的に業務改善を考えるきっかけとなり、組織全体の意識改革にも繋がっている好事例と言えるでしょう。
沼津市・伊東市のAI活用事例:AIが観光プランを提案!周遊促進と利便性向上へ
県内有数の観光地である沼津市と伊東市では、AIを活用して観光客の利便性を高める取り組みを行っています。
活用方法: 両市の公式観光サイトには、AIによるモデルコース作成機能が搭載されています。 利用者が「沼津港から車で3時間」「写真映え重視で大人向け」といった希望条件を入力すると、AIがその人にぴったりのオリジナル観光プランを提案してくれます。
成果: この機能により、観光客はガイドブックやウェブサイトを長時間見比べることなく、手軽に自分のニーズに合った情報を得ることができます。これまで知られていなかった穴場スポットへの誘導や、市内の周遊促進にも繋がり、地域全体の観光消費額向上に貢献することが期待されています。
静岡空港の生成AI活用事例:インバウンド向け「生成AI観光ナビ」で新たな観光体験を創出
日本の空の玄関口である静岡空港では、2025年2月から、訪日外国人観光客を対象とした「生成AI観光ナビ」の実証実験が開始されました。
活用方法: このプロジェクトは、NTTデータMSE、静鉄グループ、トヨタレンタリース静岡などが連携して実施。空港でレンタカーを借りる訪日客に専用のタブレットを配布し、搭載された生成AIが、利用者の母国語で対話しながら、好みや目的地に応じた県内のおすすめ観光地や立ち寄りスポットを提案し、そのままカーナビとして経路案内も行います。
成果: 有名観光地への一極集中(オーバーツーリズム)を緩和し、まだあまり知られていない県内各地の魅力的な場所へと観光客を誘導することが大きな狙いです。 AIとの対話を通じて、偶然の出会いや発見といった新たな観光の楽しみ方を提供し、静岡県のファンを増やすこと、そして地域経済の活性化を目指しています。
静岡大学:AI人材育成から社会課題解決まで
静岡大学は、地域の知の拠点として、AIに関する教育と研究の両面で先進的な取り組みを進めています。
- AI人材の育成: 全学部生を対象とした「数理データサイエンスAI教育プログラム」を提供し、文系・理系を問わず、すべての学生がAIの基礎から応用までを学べる環境を整備しています。
- 社会課題解決への応用: 2019年には「ケア情報学研究所」を設立。 高齢者の心身の健康に関する多様なデータを収集・分析する「マルチモーダルAI」という独自技術を軸に、認知症の人の自立支援など、超高齢社会の課題解決に向けた研究開発を行っています。
- AI時代のキャリア教育: 2025年4月には、楽器メーカーのヤマハと共同で、デジタル教材「人生を楽しむための余暇図鑑」を開発・公開しました。 AIによって仕事のあり方が変わる未来を見据え、子どもたちが仕事だけでなく、趣味や社会活動といった「余暇」も含めて豊かに人生を設計できるよう、新たなキャリア教育の形を提案しています。
静岡県教育委員会:教育現場での適切なAI利用を促進
生成AIの急速な普及を受け、静岡県教育委員会は、県内の学校における適切なAI利用のためのガイドラインを策定しました。
内容: このガイドラインでは、生成AIの回答には誤りが含まれる可能性があること、著作権を侵害しないこと、個人情報を入力しないことといった基本的な注意点を明記。その上で、安易に答えを求めるのではなく、自分の考えを深めるためのツールとして活用することや、情報が正しいかどうかを複数の情報源で確認する習慣を身につけることの重要性を説いています。
成果: これにより、教員も生徒も、生成AIのメリットを享受しつつ、そのリスクを正しく理解し、批判的思考力を養いながら、安全かつ効果的にAIを活用していくための指針を得ることができます。
浜松医科大学:医療DXを推進し、地域医療の質を向上
浜松医科大学は、Amazon Web Services(AWS)ジャパンとの協業を発表し、クラウドや生成AIといった最新技術を活用した「医療DX(デジタルトランスフォーメーション)」の推進に取り組んでいます。
活用方法: この協業により、大学が持つ医療に関する知見と、AWSが持つ高度なデジタル技術を組み合わせ、静岡県の医療提供体制の構築を技術面から支援します。 具体的には、現場での生成AI活用などが検討されています。
成果: 地域医療の質の向上と持続可能性の確保に貢献し、県民がより高度で安心な医療を受けられる体制づくりを目指します。
静岡県:AIでケアプラン作成を支援し、業務効率化と質向上を実現
静岡県は、介護分野におけるAI活用にも積極的に取り組んでいます。2025年3月には、「ケアマネジメント業務AI導入支援事業」として、AIがケアプラン作成を支援するシステム「SOIN(そわん)」の実証事業の成果を報告しました。
活用方法: このシステムは、介護を受ける人の状態や希望を入力すると、AIが膨大なデータに基づき、最適なケアプランの選択肢を複数提案してくれるものです。県内の居宅介護支援事業所などに所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)に利用してもらい、その効果を検証しました。
成果: AIの支援により、ケアマネジャーはより多角的な視点からプランを検討できるようになり、ケアプランの質の向上が期待されます。また、プラン作成にかかる時間が短縮されることで、本来の業務である利用者やその家族とのコミュニケーションに、より多くの時間を割けるようになるなど、業務全体の効率化と質の向上に繋がっています。
静岡銀行:AIヘルプデスクで全店の業務を効率化
地域経済の要である静岡銀行では、行員の業務効率化を目的として、PKSHA社の「PKSHA AIヘルプデスク」を全店で導入しています。
活用方法: これは、行内の様々な規定やマニュアルに関する問い合わせに対し、生成AIが関連ドキュメントを瞬時に検索し、自動で回答を生成するシステムです。
成果: これまで担当部署の職員が一件一件対応していた問い合わせ業務をAIが代替することで、行員は時間を節約し、顧客対応など、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。
鈴与システムテクノロジー:AI面接サービスで採用DXを推進
静岡に本社を置く鈴与システムテクノロジーは、2025年8月、AIを活用した採用DXの推進を発表しました。
活用方法: 対話型のAIが応募者の面接を行うサービス「PeopleX AI面接」を自社の採用活動に導入。これにより、応募者は時間や場所を問われずに面接を受けられるようになり、採用担当者の負担も軽減されます。さらに、同社はこのサービスのパートナーとして、静岡県内の地域企業への導入支援も展開していく計画です。
成果: 採用プロセスの効率化と公平性を高めるとともに、地域全体の採用力強化とDX化を後押しすることで、地域創生への貢献を目指しています。
終わりに
今回調査した事例から見えてくるのは、静岡県が生成AIを単なる業務効率化のツールとして捉えるだけでなく、「地域の課題を解決し、県民の幸福度を高めるためのエンジン」として位置づけ、多様な分野でその可能性を追求している姿です。
県庁自らが旗振り役となって全庁導入や中小企業支援を進めるトップダウンのアプローチと、藤枝市や沼津市、そして多くの民間企業や大学が実践するボトムアップの取り組みが両輪となり、地域全体でAI活用のエコシステムが形成されつつあります。
特に、観光、医療、介護、教育といった、まさに県民の生活や地域の魅力に直結する分野で、人々の暮らしをより豊かにするための具体的な活用が進んでいる点は、他の地域のモデルケースとなり得るでしょう。
もちろん、個人情報の保護や情報の正確性といった課題は存在しますが、静岡県教育委員会がガイドラインを策定したように、リスクと向き合いながら活用を進めようという真摯な姿勢も伺えます。
今後、これらの取り組みがさらに深化し、それぞれの成功事例が連携していくことで、静岡県は「AIを活用した地方創生」のトップランナーとして、ますます存在感を高めていくに違いありません。