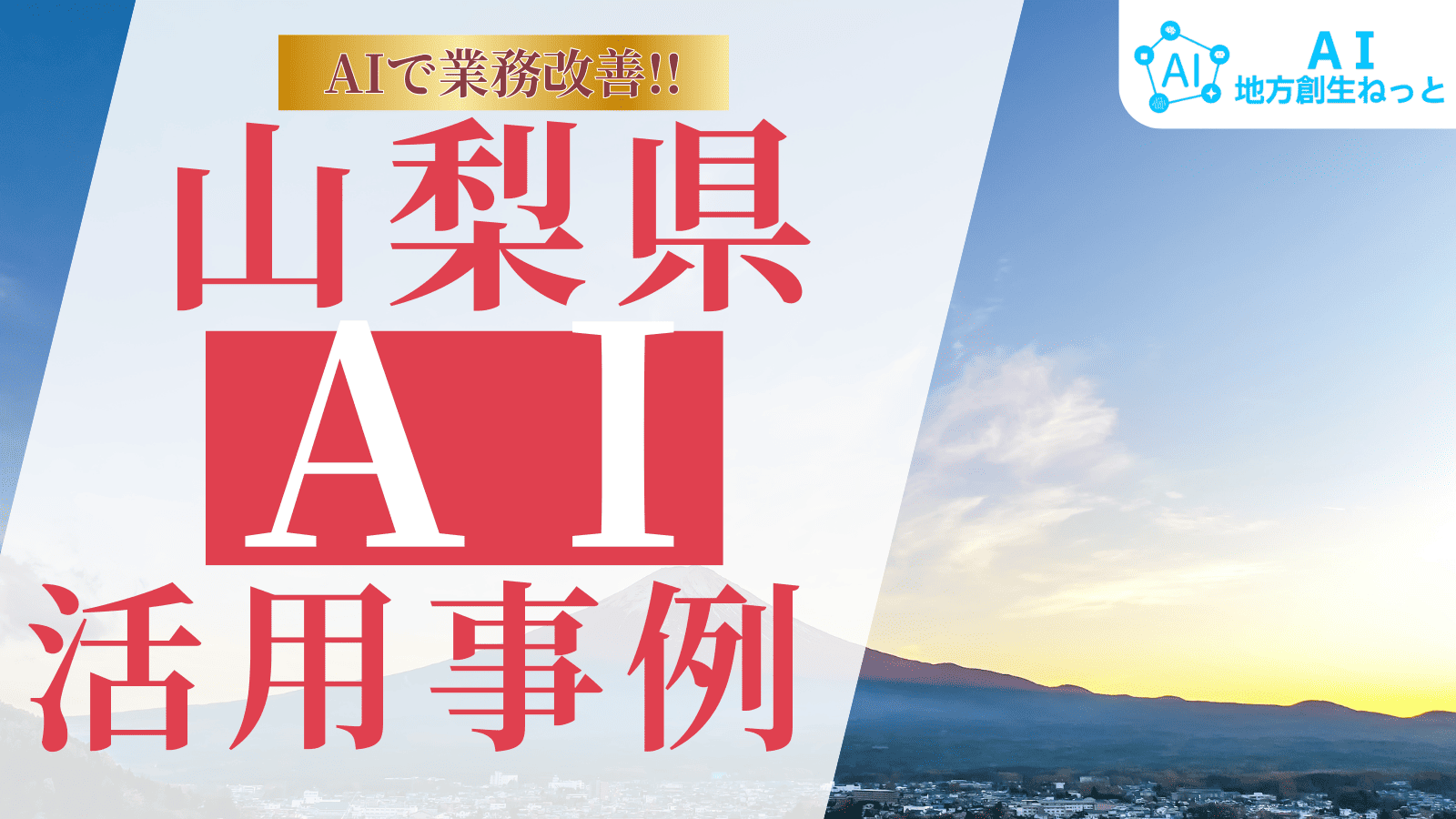自然豊かな山梨県でも、AI技術を地域課題の解決や産業振興に活かしようとする動きが活発化しています。県庁や市町村といった行政機関での業務効率化はもちろん、農業、医療、観光、教育といった多様な分野で、地域を元気にするためのユニークな取り組みが次々と生まれています。
この記事では、山梨県に焦点を当て、自治体や地域に根差した企業、団体がどのようにAIを活用し、地方創生や地域活性化に挑んでいるのか、具体的な事例を詳しくご紹介します。自治体関係者の方、地域活性化に興味があるビジネス層の方、そしてAIの可能性に関心を持つすべての方にとって、有益な情報となれば幸いです。

水野倫太郎
(株)ICHIZEN HOLDINGS
代表取締役
慶應義塾大学経済学部卒。2017年米国留学時ブロックチェーンと出会う。2018年仮想通貨メディアCoinOtaku入社。2019年同社のCMO就任、2020年に東証二部上場企業とM&A。2022年(株)ICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ、Web3事業のコンサルティングをNTTをはじめとした大企業から海外プロジェクト、地方自治体へ行う。ブロックチェーンだけでなく生成AI導入による業務効率化を自治体中心に支援中。

監修 水野倫太郎
(株)ICHIZEN HOLDINGS
代表取締役
慶應義塾大学経済学部卒。2017年米国留学時ブロックチェーンと出会う。2018年仮想通貨メディアCoinOtaku入社。2019年同社のCMO就任、2020年に東証二部上場企業とM&A。2022年(株)ICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ、Web3事業のコンサルティングをNTTをはじめとした大企業から海外プロジェクト、地方自治体へ行う。ブロックチェーンだけでなく生成AI導入による業務効率化を自治体中心に支援中。
【山梨県庁】生成AIで行政を効率化、県民サービス向上へ
山梨県庁は、行政サービスの質の向上と業務の効率化を目指し、AI技術の導入を積極的に進めています。
活用事例:Microsoftの生成AIによる議会答弁・文書作成支援
【活用事例の概要】 山梨県は2024年6月、アビームコンサルティング株式会社の支援を受け、Microsoft社のAzure OpenAI Serviceを活用した独自の生成AI利用環境を構築しました。 この取り組みは、知事のリーダーシップのもと、2023年6月頃から検討が開始されたものです。
【活用方法】 このシステムは、過去の議会答弁や財務規則といった県が保有する膨大な行政文書をAIに学習させた、いわば「山梨県庁専門のAIアシスタント」です。職員は普段使っているビジネスチャットツール「Microsoft Teams」から、AIに対して質問や指示を出すだけで、必要な情報を引き出したり、文書のたたき台を作成させたりすることができます。
【成果】 このAIの導入により、これまで職員が多くの時間を費やしていた議会答弁の準備や、財務会計に関する問い合わせへの回答作成といった業務が大幅に効率化されました。 AIが作成したたたき台を元に職員が内容を修正・加筆することで、より質の高い成果を、より短時間で生み出すことが可能になったのです。県は今後、この仕組みをさらに多くの業務に応用していく方針です。
【富士川町】AI案内ロボットが職員に代わって窓口業務
人口減少や高齢化が進む中で、多くの地方自治体が直面する「人手不足」。南巨摩郡富士川町では、この課題にAIロボットで立ち向かう先進的な実証実験が始まっています。
活用事例:AI案内ロボット「Timo」による窓口業務の自動化
【活用事例の概要】 富士川町は2024年6月25日、一般社団法人公民連携推進機構(DFA)と連携し、庁舎内にAI案内ロボット「Timo(ティモ)」を導入する実証実験を開始しました。
【活用方法】 「Timo」は、来庁者の音声やタッチパネルでの質問を認識し、庁舎内の目的地や手続きについて案内するAIロボットです。例えば、「住民票が欲しいのですが」「税金の相談はどこですか?」といった質問に対し、適切な課の場所や行き方を音声と画面表示でガイドします。
【成果・目的】 この実証実験の最大の目的は、職員の業務負担軽減と省人化です。これまで職員が対応していた窓口案内業務をロボットが代替することで、職員はより専門的な業務や住民への丁寧な対応に集中できるようになります。富士川町では、この実験を通じてAIロボット導入の効果を検証し、本格的な導入と人手不足問題の解決を目指しています。
【富士河口湖町】AIで観光情報を集約!オーバーツーリズム対策にも
世界的な観光地である富士河口湖町では、観光客の満足度向上と、一部地域への観光客集中(オーバーツーリズム)という課題解決のためにAIが一役買っています。
活用事例:AIイベント情報集約サイトによる周遊促進
【活用事例の概要】 富士河口湖町は2024年6月、株式会社インフォモーションの「AIイベント集約サービス」を導入し、「富士河口湖イベント情報集約サイト」を公開しました。
【活用方法】 このサイトの最大の特徴は、AIがインターネット上にある様々なウェブサイトから、富士河口湖町で開催されるイベント情報を自動で収集・集約している点です。大規模な公式イベントから個人主催の小さな催しまで、これまで点在していて見つけにくかった情報が、このサイト一つで網羅的にチェックできます。
【成果】 観光客や町民は、キーワードや日付、エリアなどで簡単にイベントを検索できるようになり、利便性が大幅に向上しました。これにより、これまで知られていなかったイベントや場所に光が当たり、観光客が町内を幅広く周遊することが期待されています。結果として、特定スポットへの過度な集中が緩和され、オーバーツーリズム問題の解消にも繋がる画期的な取り組みとして注目されています。
【教育現場】AIが先生の働き方改革と、子どもたちの未来の学びを支援
山梨県の教育現場では、AIを「未来を担う子どもたちのためのツール」そして「多忙な教員の業務を支えるパートナー」として活用する動きが広がっています。
活用事例:甲府市立石田小学校の「生成AIパイロット校」としての挑戦
【活用事例の概要】 甲府市立石田小学校は、文部科学省が指定する「生成AIパイロット校」として、全国に先駆けてAIの教育活用を実践しています。
【活用方法】 教員の活用場面は多岐にわたります。例えば、総合的な学習の指導案のアイデア出し、保護者へのお便りのたたき台作成、学校行事後のアンケート集計など、校務の様々な場面でAIを活用し、業務のスマート化を図っています。 一方、児童たちもAIに触れる機会が設けられています。6年生の授業では、AIが書いた文章と小説家が書いた文章を比較し、「人間ならではの創造力とは何か」を考えるといった、AIリテラシーを育むユニークな授業も行われました。
【成果】 教員にとっては、文書作成などにかかる時間が短縮され、子どもたちと向き合う時間をより多く確保できるというメリットが生まれています。児童にとっては、AIを身近なツールとして正しく理解し、これからの社会で求められる思考力や創造力を養う貴重な機会となっています。
【農業】AIが匠の技を継承し、未来の食を支える
フルーツ王国・山梨の基幹産業である農業。高齢化や担い手不足という課題に対し、AIやロボット技術を活用した「スマート農業」が、持続可能な農業を実現するための鍵として期待されています。
活用事例:AIとスマートグラスによるブドウ栽培技術の継承
【活用事例の概要】 高品質なブドウ「シャインマスカット」の栽培には、「摘粒(てきりゅう)」という、余分な実を間引いて房の形を整える繊細な作業が欠かせません。この作業は熟練の経験と勘が求められますが、山梨大学などはAIを活用してこの「匠の技」を誰もが実践できるシステムを開発しています。
【活用方法】 作業者は、AIが搭載されたスマートグラスを装着します。グラスのカメラがブドウの房を映すと、AIが最適な粒の数や配置を瞬時に判断し、「どの粒を切ればよいか」をディスプレイ上に表示してくれます。作業者はその指示に従うだけで、ベテラン農家のような高品質な摘粒作業ができるようになります。
【成果】 この技術により、経験の浅い新規就農者やパートタイマーでも、質の高いブドウ栽培が可能になります。深刻化する担い手不足の解消や、熟練農家が持つ貴重な技術の次世代へのスムーズな継承が期待されています。将来的には、AIが自律的に作業を行う摘粒ロボットの実用化も目指されています。
【医療・健康】AIが病気の早期発見と健康寿命の延伸をサポート
県民の健康を守る医療・健康分野でも、AIの活用が進んでいます。AIは、医師の診断をサポートしたり、人々が自らの健康を管理するのを手助けしたりと、様々な形で貢献しています。
活用事例:AIによる骨粗しょう症の早期発見プロジェクト
【活用事例の概要】 山梨県は、企業の健康診断などを活用し、骨がもろくなる病気「骨粗しょう症」を早期に発見するための実証実験を行っています。この取り組みには、iSurgery株式会社が開発したAI医療機器が活用されています。
【活用方法】 このAIは、健康診断で撮影された「胸部X線写真」を解析し、骨の状態を評価することができます。受診者は、特別な検査を追加することなく、既存のレントゲン写真から骨粗しょう症のリスクを知ることが可能です。
【成果】 自覚症状がないまま進行することが多い骨粗しょう症のリスクを、健康診断という身近な機会に発見できるのが大きなメリットです。リスクが高いと判断された人には専門外来の受診が推奨され、早期の治療介入につながります。これにより、将来の骨折を防ぎ、県民の健康寿命の延伸と医療費の削減効果が期待されています。
終わりに
この記事では、山梨県におけるAI活用の多様な事例をご紹介しました。
行政サービスの効率化から、農業や医療といった専門分野での技術革新、さらには観光振興や教育現場の支援まで、AIが地域社会の様々な課題解決に貢献し始めていることがお分かりいただけたかと思います。
特に、山梨県の取り組みで印象的なのは、県が「TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業」などを通じて、スタートアップ企業や大学と積極的に連携し、AIのような先端技術を地域課題に結びつける「実証実験の聖地」としての役割を担っている点です。 これは、単にAIツールを導入するだけでなく、地域全体で新しい価値を共創していこうという強い意志の表れと言えるでしょう。
もちろん、AIの導入はゴールではありません。AIをいかに「使いこなし」、真に豊かで持続可能な地域社会を築いていくか。山梨県の挑戦は、全国の自治体や企業にとっても、多くのヒントを与えてくれるはずです。今後も、山梨県から生まれる未来志向の取り組みから目が離せません。