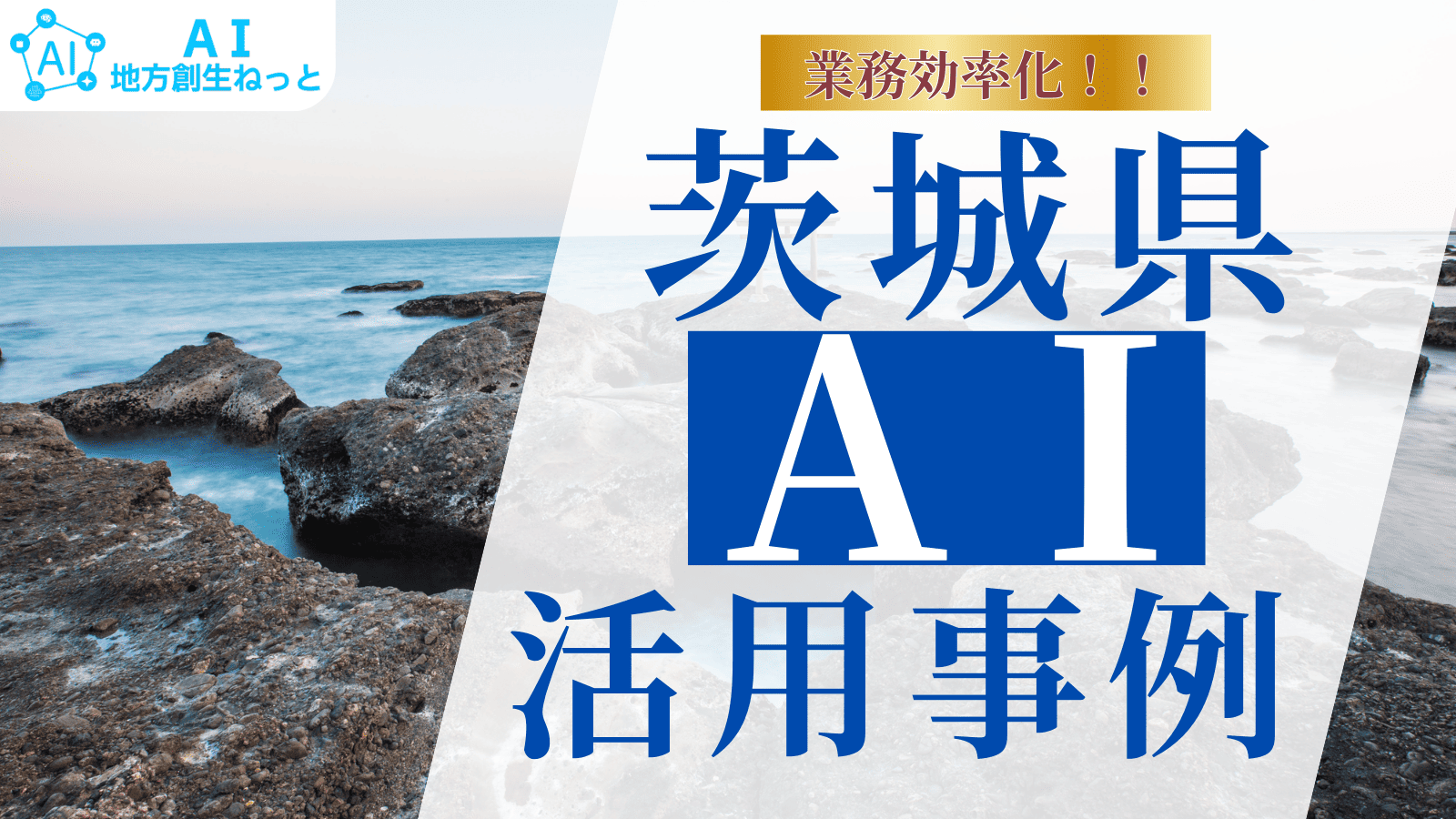茨城県では、各地方自治体がChatGPT等を生成AI用いた業務効率化に力を入れています。
この記事ではそんな茨城県における生成AIの活用事例を紹介していきます。

水野倫太郎
(株)ICHIZEN HOLDINGS
代表取締役
慶應義塾大学経済学部卒。2017年米国留学時ブロックチェーンと出会う。2018年仮想通貨メディアCoinOtaku入社。2019年同社のCMO就任、2020年に東証二部上場企業とM&A。2022年(株)ICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ、Web3事業のコンサルティングをNTTをはじめとした大企業から海外プロジェクト、地方自治体へ行う。ブロックチェーンだけでなく生成AI導入による業務効率化を自治体中心に支援中。

監修 水野倫太郎
(株)ICHIZEN HOLDINGS
代表取締役
慶應義塾大学経済学部卒。2017年米国留学時ブロックチェーンと出会う。2018年仮想通貨メディアCoinOtaku入社。2019年同社のCMO就任、2020年に東証二部上場企業とM&A。2022年(株)ICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ、Web3事業のコンサルティングをNTTをはじめとした大企業から海外プロジェクト、地方自治体へ行う。ブロックチェーンだけでなく生成AI導入による業務効率化を自治体中心に支援中。
茨城県のAI活用事例① 茨城県庁:業務効率化と行政サービス向上を実現
茨城県庁は、生成AI技術を活用して行政業務の効率化と県民サービスの向上を目指しています。特に、文書作成や情報検索、政策提案の補助に生成AIを活用することで、職員の負担を軽減し、よりスピーディーで高品質なサービスを提供することを目的としています。
茨城県庁では、2023年6月から7月にかけて、ChatGPTとGoogle Bardを試験的に導入しました。これらのツールを利用して、職員が作成する報告書や議事録、政策提案書などをAIが草案として作成し、職員がその内容を修正・調整するという形で業務を効率化しました。また、AIは過去のデータを基に新しいアイデアを提供し、政策立案やプロジェクト計画を迅速に進めるための支援も行いました。
試験導入の結果、職員一人あたり約200時間の作業時間を削減できることが分かり、業務の効率化が実現しました。特に、文書作成の時間短縮が大きな成果となり、職員がより創造的な業務に時間を割けるようになりました。2024年4月からは全庁に本格展開されており、さらなる効率化とサービス向上が進められています。
茨城県のAI活用事例② つくば市:市民サービスの向上と業務の効率化
つくば市は、生成AIを活用して市民サービスを向上させ、同時に行政業務の効率化を図っています。市民からの問い合わせ対応や広報活動に生成AIを活用し、住民に迅速に情報を提供する体制を整えました。
つくば市では、2023年5月にChatGPTを市の広報や政策提案書作成に活用し始めました。特に、市民への情報提供を効率化するために、広報誌の記事やお知らせをAIが作成し、職員はその内容を確認して調整するという方法を取り入れました。また、市民からの問い合わせ対応には、AIチャットボットを導入し、24時間対応可能な体制を整えています。このチャットボットは、税金の支払い方法や子育て支援など、よくある質問に自動で回答します。
生成AIの活用により、市民への情報提供が迅速化され、職員の負担が軽減されました。AIチャットボットによる問い合わせ対応が導入されたことで、自治体窓口の負担が減り、職員はより専門的な業務に集中できるようになりました。今後は、さらに多くの市民サービスに生成AIを導入し、業務効率化を進めていく予定です。
茨城県のAI活用事例③ 笠間市:生成AIを活用した広報文書の効率化
笠間市は、生成AIを活用して広報業務を効率化し、市民への情報提供をより迅速で分かりやすく行うことを目的としています。特に、広報文書の作成にAIを活用することで、職員の作業負担を軽減し、より効果的な情報発信を実現しています。
笠間市では、生成AIを利用して広報文書の作成支援を行っています。具体的には、2023年10月から、ChatGPTを使用して、広報誌や市民向けのお知らせ文書の草案を作成しています。AIは、過去の広報文書や自治体の方針を基に、新しい内容を提案し、職員はその内容を基に修正を加える形で作業を進めています。この方法によって、従来の手作業よりも効率よく文書作成を進めることができ、広報活動をより迅速に行えるようになりました。
生成AIを活用することで、広報文書作成の時間が大幅に短縮され、職員は他の重要な業務に時間を割けるようになりました。市民からも「情報提供が迅速になった」「内容が分かりやすくなった」といった好評を得ており、今後は広報文書だけでなく、その他の行政文書にも生成AIを活用していく予定です。これにより、さらに業務効率化が進むことが期待されています。
茨城県のAI活用事例④ 鹿嶋市:生成AIによる議会答弁支援
鹿嶋市は、生成AIを活用して議会答弁の作成支援を行っています。議会での答弁作成にかかる時間を短縮し、職員の負担を軽減することが目的です。特に、答弁内容の精度を高め、市民に対する説明責任を果たすために生成AIを活用しています。
鹿嶋市では、2023年11月から、ChatGPTを活用して議会答弁案を作成しています。市長や議員が受けた質問に対して、AIが過去の議事録や関連資料を基に自動的に答弁案を作成し、その後、職員が内容を確認・修正して本番の答弁を作成します。このプロセスによって、答弁作成のスピードが向上し、職員は他の業務に時間を割くことができるようになりました。
議会答弁の作成が効率化されたことで、職員の作業負担が軽減されました。また、AIが提供する新たな視点が加わることで、答弁内容の精度も向上しました。今後は、議会答弁だけでなく、他の行政文書作成にも生成AIを活用し、さらに効率化を進める予定です。
茨城県のAI活用事例⑤ 取手市:生成AIを活用した音声認識議事録
取手市は、議会や会議の議事録作成を生成AIと音声認識技術を組み合わせることで効率化しました。議事録作成にかかる手間を削減し、会議後すぐに議事録を提供できるようにすることが目的です。また、議事録の精度を向上させることも狙いの一つです。
取手市では、会議の音声をリアルタイムで認識し、その内容を音声認識AIが自動で文字起こしします。その後、ChatGPTを使って議事録の要約や重要なポイントを抽出し、職員がそれを基に最終的な議事録を作成します。このプロセスにより、議事録作成の時間が大幅に短縮され、会議終了後すぐに内容を確認できるようになりました。
議事録作成の効率化により、会議後の遅延が解消され、市民や議会関係者に迅速に情報を提供できるようになりました。また、音声認識と生成AIを組み合わせることで、議事録の精度も向上し、誤字脱字や内容の漏れを減少させることができました。今後は、さらに多くの会議でこの技術を活用し、行政業務の効率化を進める予定です。